|
第25回
|
2002年1月31日 菱川貞義 |
| 常識と真実の力関係 | |||||||||
| “常識”と“真実”を比較することは常識で見るとナンセンスです。なのになぜ比較するかというと、いまの世の中はあまりにも常識と真実のバランスが崩れているように思えるからです。“常識”はどんどん岩のようにかたく大きくなりながら、私たちから疑う視力をうばい、“真実”はますます砂つぶのように小さく、目に見えなくなってきている気がします。 |
|||||||||
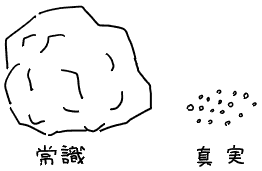 |
ちょっと古い辞典ですが、岩波書店の広辞苑(第二版補訂版)を引いてみると、常識は『普通一般人が持ち、また、持っているべき標準知力。専門知識でない一般的知識とともに理解力・判断力・思慮分別などを含む。』とあり、真実は『いつわりでないこと。ほんとう。まこと。』とあります。 ここでぼくが気になるのは、「常識は一時的に有効な知識でしかないが、真実を感じるということは普遍的な知恵に出会うことにつながる」ということに触れていない点です。 |
||||||||
| 歴史をさかのぼって眺めてみると、いつの時代から見ても、となりの時代の常識はまったく役に立ちません。江戸時代の常識が明治時代に役に立つでしょうか。ほかの時代はどうでしょうか。また、どの国から見ても、となりの国の常識もまた、あまり役には立ちません。牛は全世界で食品として扱われているのでしょうか。さらに行政、企業、農家、住民といった立場の違いによる常識といったものは、お互いをよく知り、ひとつの地球を守り育てながら豊かなくらしを営んでいくことにどれほど役に立つのでしょうか。 |
|||||||||
| 例えば、地球温暖化問題のことを知れば知るほど、考えれば考えるほど、常識と真実の力関係を憂います。地球の真実としてほんの一部の人間たちにとっての都合でしかないものを、常識として全世界に押しつけようとしています。「世界経済にとって炭素排出をおさえるのは、生産をおさえるのは常識的ではない」と。様々な真実が地球温暖化に対して警告しているにもかかわらず。 “一部の人間たち”から“都合のよい常識”というメガネをはずすにはどうしたらいいのでしょうか。“一部の人間たち”の目をもう少し真実に向けさせてあげるために、私たち一人ひとりが、まずもっと真実をよく見つめなければならないでしょう。 |
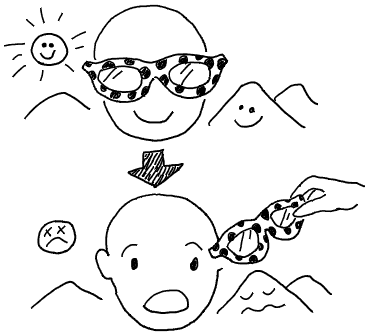 |
||||||||
| また、少し次のことを考えてみてください。 | |||||||||
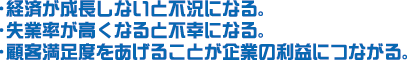 |
|||||||||
|
Copyright (C)2001 Biwako
Shimin Kenkyusho all rights reserved
|
|