西川嘉右衛門商店会長
| 西川嘉廣さん 西川嘉右衛門商店会長 |
| |
|
|
|
| ヨシ博物館とは? |
|||
| 第114回 | 青二才のヨシに注目 |
| 2004年9月9日 菱川貞義 |
 |
|
西の湖で何やら、青いヨシの実験ほ場があるというので、8月10日に丹波さんに案内してもらいました。東近江ではいよいよヨシのビジネス化に向けて本格的に動きはじめています。 「ちょっと気軽に見学を…」と思っていたのに、ほんとうに東近江水環境自治協議会はこわいところです。なんと!現地に来てみると、西川会長や安居副会長をはじめ、そうそうたるメンバーが集結していました。 |
 |
 |
京都嵯峨芸術大学から金氏先生、百木先生、琵琶湖研究所からは統括研究員の西野さんが来られていました。重野さんや安土町商工会事務局長の野瀬さんもおられます。 |
 |
 |
| (丹波さん) ヨシ刈りをボランティアではなく、なんとか、むかしのようにヨシをビジネスに結びつけて、ヨシ刈りの手間賃が出るようにしたいんです。 ヨシというと、枯れたヨシを想像しますが、われわれの小グループで考えているヨシの商品化は青いヨシをつかったものが多いんです。 |
 |
 |
これはヨシを乳酸発酵させる実験です。ちょっと漬物のようなニオイがしますでしょ。 これを牛に食べさせようか、と思っています。また、西の湖からあげた泥にこれを混ぜ込んで緑肥にできないか、ということも… |
 <5月23日に刈ったところ> <5月23日に刈ったところ> |
 <6月19日に刈ったところ> <6月19日に刈ったところ> |
ここではヨシの成育状況の実験を行なっています。区域を分けまして、青いヨシをそれぞれ刈る高さを変えてみました。20cm、40cm、60cmで刈るとどうなるか。また、肥料を入れたのと入れないのでの違いはどうか。5月23日に刈りました。 さらに、一月おくれで6月19日に刈った区域もあります。 来年はさらにいろんな時期に刈ってみようと思っています。 |
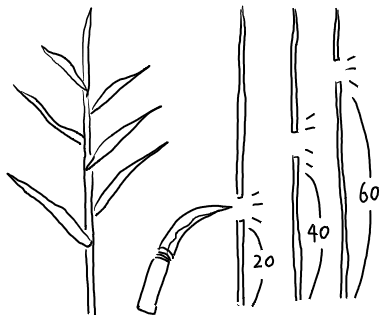 |
 |
3、4メートルもあるヨシのジャングルのなかを分け入ると、ヨシ原のなかはほんとうにワクワクする別世界です。 このヨシ原で東近江水環境自治協議会はかなり詳細な実験を行なっており、こちらは興味津々ですが、その驚くべき成果の発表はもう少しお待ちください。 ただこの見学で強く感じたのは、「ヨシの生きる力ってすごい!」ということです。 |
最近、ヨシ原に来ると、何やらヨシが語りかけてくるような気がするのはどういうことなんでしょうか?少しヨシとなかヨシになったということでしょうか? |
 |
(つづく) |