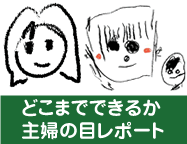
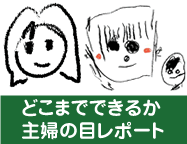 |
|
|||||||||||
| ゆうこ 25回 | 2002年10月24日 | |||||||||||
| 朽木村での不耕起のしぜ〜んな拡がり方 <その2>山本隆男さん |
|||||||||||
 |
山本隆男さんの住む雲洞谷家一(うとだにえべつ)地区は、朽木村のちょうど真ん中あたり。 家が一つと書いて家一(えべつ)。どうしてそう読むのか不思議ですが、どうもアイヌ語のようです。 「家一と書くけど、ここは昔から家は10軒。減ると必ずまた新しい人が来て、いつも10軒なんですよ。」と山本さんの奥さんに聞きました。朽木村にアイヌ語の地名?なぜ?昔からいつも必ず10軒? 不思議な話にますます興味がわく朽木村です。 |
||||||||||
| 1反の田んぼが人生を変えた 2年前、たまたま起こしていない1反ちょっとの田んぼがあまっていて澤田くんから「起こさんかて、田植えは出来てんぞ!!やってみいひんか?」「やってみてくれ」言われて「ほんまけ?いっぺんやってみようか?」ってことでわしは管理させてもろうたんやけど。不思議なことにな、その1反ちょっとの田んぼが、わしに貴重な数々の体験をさせてくれたんや。 |
|||||||||||
| 最初はこんな草だらけのところに田植えして、どうもないんかな?思ったんや。ところが植えて1週間もしたら、ああ何と、りっぱになってくるんやな。 それからずーっと1年間観察してみた。 そうすると「これは違う!」たしかに米が違う!というような事で、米の評価は収穫してから、正月にもちをついてからわかった。 このもち米でついた餅がすごくうまかったんや。朝市出したらお客さんがちゃんと言うてくれた。 もちの味が違う! おいしい! って |
 |
||||||||||
| 田んぼに案内してもらいました。田んぼは杉の山々に囲まれた静かな山の中の田んぼです。 ここで山本さんは、朝市で販売している鯖ずし用の米と、とち餅、白餅などもち加工用のもち米を作っています。 稲はもうずっしり重い穂を垂れていて、たわわに実る、とはこういう事だと思いました。 |
|||||||||||
 |
(山本さん) |
||||||||||
 |
|||||||||||
| そんな山本さんも3年前までは慣行農法でやっていたそうです。 昭和30年頃からやな、百姓が変わってしまったのは。農薬、肥料をバンバンやってきたんやから。 「そうせな田んぼは植わらん!!」と思っていたんや。それが人生変わるほど、180°の転換や。今思うと不思議なことやな、澤田君がいうてくれて、やってみた1反の田んぼがわしの米作りの人生を変えたんや。 わしが一番思うたことは、滋賀県は真ん中に琵琶湖があって、田んぼがあって、山がある、環境のいいところなんやわ。この山の上からわしらが汚していくさかいに、琵琶湖がひどいもんや。農家が目覚めてくれたら、もっともっと琵琶湖の水はきれいになると思う。なるんや! |
|||||||||||
| そういえば、澤田龍治さんは山本さんのことをこんなふうに言っていました。 「山本さんはもう一生懸命や、田んぼもよう観察しとるし、いい事はすぐ実践しはる!とにかく一生懸命勉強しはるからな」 山本さんも不耕起をはじめられた感謝の気持ちをこう話されていました。 「澤田くんのおかげや。澤田くんはえらいなと思う」 こうして朽木村では澤田さんから山本さんへ、またその信頼で他の人へ、という信頼の輪で不耕起が自然に拡がっているようでした。 山本さんの話を聞いていると、勇気がわいてきます。 不耕起をする、ということは今まで自分がやってきたことを否定することでもあるのに、真剣に田んぼに向き合って、1年でこれまでの米作りの考え方を一変することができたんです。 |
 |
||||||||||
 |
「人間、まだまだ今の自分から180°変わる事ができるんだ!!」 と勇気づけられます。 ただし、耳を傾けて心を開く勇気と、行動を起こす勇気が必要です。 次回は、山本さん夫妻に伺った、朽木村の「昔の暮らし物語」をお伝えします。 |
||||||||||
|
(つづく) |
|||||||||||
|
Copyright (C)2001 Biwako Shimin
Kenkyusho all rights reserved
|
|||