|
|
|
第15回
|
2001年11月15日 菱川貞義 |
| 戦争と環境問題 |
|
先々週に登場していただいた笹谷先生と同じ立命館大学(学部はちがいますが)で、環境にかかわっておられる経営学部・環境経営論の平井孝治先生にもお会いしました。 |
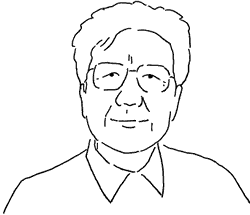 |
|
「ミッション広告が21世紀の企業には必要になる。“どういう価値を創造するのか”を見つめる。“顧客満足を追及する”ではダメ。単に顧客の要望を聞いていたのでは環境負荷を高くすることも多いからだ。そうではなく、“パブリックな価値”を追及するべきだ。」 |
 |
|
「環境派の真価が問われている。アフガンを環境問題の視点から考えているのか。環境のどこに目を向けているのかを問いたい。環境問題はグローバルな問題のはずだ。テロを許しているわけじゃないがアフガンの干ばつやハンセン病等に対しても、日本ももっと目を向けないとだめ。できることは小さくてもいっぱいできる。戦争は環境問題そのものだ。環境サイトでもこのことを取りあげて当然のはずだ。」
「他の問題を軽んじているのではない。しかし、目を向けないのはなぜ?“自分たちだけを守る”という発想は環境じゃない。琵琶湖もアフガンも同じに大切。といいながら個人的な焦りもある。この挑戦に対する意見広告とかいろんな手だてを考えているところだ。」 「環境問題と報復との関係を見直す必要がある。環境教育や市民運動の中でも。琵琶湖に爆弾が落ちたらと考えたことがあるのか。琵琶湖が灰になったら、いまの我々の環境運動はどうなるのか。“真のグローバル、共生”は環境経営、環境管理にとって一番重要。環境教育でも一番重要。市民運動としても一番重要。」 「環境を学んでいながら、報復が当たり前だという学生に失望している。そこに自分の考えがない。考える主体が確立されていない。」 みなさんはいかが感じておられますか? |
|
Copyright (C)2001 Biwako
Shimin Kenkyusho all rights reserved
|
|