|
|
|
第16回
|
2001年11月22日 菱川貞義 |
| 農業への新しいまなざし |
|
琵琶湖研究所において、10月11日に第38回・琵琶湖セミナー「水田の生物多様性保全」がありました。そこでぼくは、農業の新しいまなざしに出会いました。 |
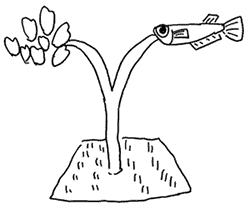
|
|
日本人の自然観は2つのもので混乱している。明治以降に生まれた2つの自然観のひとつは「人間が手を加えない自然」、もうひとつは「農業で生まれた赤トンボなど人間の手を加えた自然環境」。そのなかで「人間の手が加わらないと育たない」自然が軽んじられている。農学が対象にしていなかった「農業こそが自然環境を守ってきた」という考え方が農業を守ることになる。 |
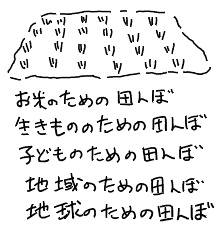 |
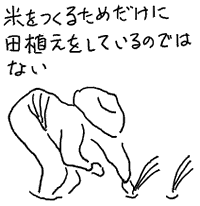 |
若い世代は、まわりに生きものが少ないから生命とのかかわりができない、だから生命を大切にできない。生きものを増やせば、自然と生きものとつきあうことになり、大切にもする。田んぼにしても、子どもに畔を走らせるだけでもりっぱな総合教育になる。そのことを教える人が育っていない。いまの教育は子どもへの語りかけがまちがっている。農業は食べ物を作るだけでなく自然環境を守る仕事だと伝えることが大事。 そうすると、手植えはみじめではなく新しい価値がでてくる。生きもの調査は趣味でなく百姓仕事として評価できるようになる。「赤トンボが何匹見つかったから給料はいくら」というような評価。 |
|
農業で自然に働きかけるのはごく一部。ほとんどは自然の力、恵みによる。だから農業の環境への仕事の評価がむずかしい。そのとき科学では分からないものがあることを認識する必要がある。なぜ、メダカが必要かは科学だけでは説明しきれない。それを科学で証明していく。感性で科学を補強する。そういうふうな議論がもっと必要。
そして市民レベルでもっと動いて政府を動かすことが重要。「本当にメダカが必要」という政策要求を突きつける。なんとなく必要というのではだめ。 「水田・環境・健康・子供たちを守る会」の仲岸希久男(専業農家)さんの講演も“新しいまなざし”にあふれていました。仲岸さんについては、「おいしいお米!」研究がスタートしましたので、そちらで次々と感じていただけることになると思います。 |
|
Copyright (C)2001 Biwako
Shimin Kenkyusho all rights reserved
|
|