|
第21回
|
2001年12月27日 菱川貞義 |
| 教材は自然の中にある |
| 近ごろ、「地球市民として実際に行動する人間を育てるためには、知識でしか理解しようとしない大人は置いといて、情緒面での理解が可能な小学生までの環境教育に力をいれることが重要だ」という意見をよく聞きます。また、子どもの脳の劇的な成長過程に目を向けたとき、「子どもがいかにふしぎであり、子どもへの環境教育がいかに大切か」について深く考えさせられます。ニューズウイーク日本版(TBSブリタニカ)で報告されている子どもの脳の成長に関する次のような記事も、驚嘆に満ちています。 |
||||||
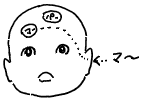 |
例えば、赤ん坊の耳に入った「マー」という音が、電気的な信号となって耳のニューロンから大脳の聴覚野へ運ばれ、神経伝達物質が放出されると、脳の細胞の一部分は永遠に「マー」という音にしか反応しなくなる。人間の脳は誕生後も、感覚や学習、記憶のための回路を形成しながら成長を続けていき、「学ぶ」ことによって初めて脳は本来の役割を果たせるようになる。 |
|||||
| 脳の回路を決めるのは先天的な要因ではなく、生まれてからの「経験」である。誕生時の人間の脳には約1000億個のニューロンと50兆以上のシナプス(神経結合)が形成されており、わずか生後数ヶ月でシナプスは20倍の1000兆以上に増えるが、これは遺伝情報だけではとてもまかないきれない数であり、「経験(外界から脳に送り込まれる信号)」によってシナプスは鍛えられていく。 ウェイン大学のチュガニの研究によると、生後6ヶ月から1年の間に、思考や論理をつかさどる前頭葉で成人の脳の2倍のエネルギーを消費しながらシナプスが形成され、その勢いは10歳になるまで続く。幼児の脳はとてつもなく柔軟であり、成長とともにその柔軟性は急速に失われていく。柔軟な時期の脳の能力形成は、母親やまわりの大人が愛情をもってどれだけ話しかけるかに大きく左右される。 |
||||||
| とても柔軟にできている子どもの脳の中では、あるひとつの経験がさまざまな能力に影響を及ぼす。1996年にニューロロジカル・リサーチ誌に発表された論文で、3、4歳児への音楽教育が子どもの数学やエンジニアリングなどの基礎的能力に役立つことが判明した。カリフォルニア大学アーバイン校のゴードン・ショーは、ピアノの鍵盤をたたいてメロディーを奏でることで、空間(鍵盤)と時間(メロディー)を結びつけるニューロンが強化されるためだと説明している。 |
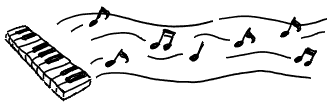 |
|||||
| これらの事実は何を語っているでしょうか。子どもの驚異の能力とともに子どもへの環境教育の大切さが伝わってきます。脳が柔軟な子どもの時期に「自然やいのち」について学ばせることが、環境と自分との強固なつながり(シナプス)を形成するのにとても役立つでしょう。そして「学び」は、学習教材による「知識」だけではなく、目の前の出来事とつながった「体験」がなければ、子どもにとっては、ただのノイズでしかないのです。様々ないのち(自然)とたくさんかかわって、楽しく過ごす経験が増えれば増えるほど、子どもは“自然を大切にする心”や“ほかのいのちとつながっている意識”を育んでいくのだと思います。 |
||||||
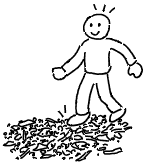 |
しかし、これらの経験は大人にも有効なはずです。大人になっても、お年寄りでさえ新しいシナプスを形成できる能力があることが分かっています。例えば「森を大切にする」という事でも、腐葉土のフカフカのじゅうたんを歩いて気持ち良かったり、森のあちこちから聞こえる小鳥のさえずりを時間を忘れて追いかけたり、おもしろい虫に出会って得した気分になったり、いのちのないハゲ山でさみしい風に吹かれたり、「うれしい」「かなしい」といった感情と結びつくと、より強く脳のシナプスが刺激されます。クッキーをたくさんもらう喜びと結びつくことで子どもが「もっと」という概念を理解しやすいのと同じように、大人の場合も感情と結びついた記憶はより鮮明に残るものなのです。 | |||||
|
Copyright (C)2001 Biwako
Shimin Kenkyusho all rights reserved
|
|