|
第22回
|
2002年1月10日 菱川貞義 |
| いのちを支える水<その1> 目に見えないが無視できないもの |
|||||||
| 来年、第3回世界水フォーラムが京都・滋賀・大阪で開催されます。これに向けた取り組みもいろんなところで活発化してきているようです。当然ながら人間は水なしでは生きていけません。でも、私たちは水のことをどれほど理解しているでしょうか。空からふってきた雨がどんな旅を経て、また雨となって地上にふり注ぐのでしょうか。その旅の途中で水はどんな目にあっているのでしょうか。 |
|||||||
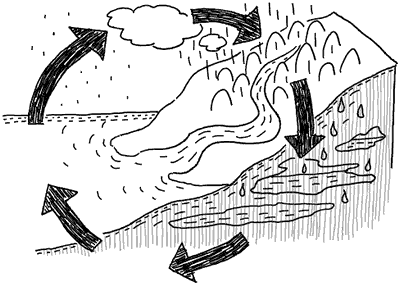 |
|||||||
| “水”といえば、すぐに湖や川や海を連想します。しかし地下水のことはつい忘れがちです。川の汚れは目に見えますが、地下水の汚れはふだん目にすることができません。しかし地下水のことをよく考えないでは、水の環境をうまくとらえることはできません。地下水は目には見えませんが、地球上の“いのち”にとって欠くことのできない存在です。 深い地下にある水の層、水を含んだ石や土、岩と岩のあいだに溜まった水、地球上に液体として存在する淡水のおよそ97%がこうした目に見えない地下に貯えられています。 河川の汚染が進み、その様子が一目瞭然となっても、地下水は土壌が完ぺきな自然のフィルターになっていると信じられ、飲料水や潅漑用水はどんどん地下水に依存するようになりましたが、当然ながら地下水も汚染されていることが、人間に驚きをもって迎えられることになってしまいました。 |
|||||||
| 地下水が汚染されているとなると、事はあまりにも重大です。ワールドウォッチ研究所の「地球白書」によれば、川の水はたった16日ぐらいで入れ替わりますが、地下水の滞留時間は平均で1400年です。帯水層内の汚染物質は、海に流しだされることも、新たな淡水が補給されて薄められることもなく、着実に蓄積していきます。そして地下水の汚染は河川とは違いほとんど取り返しがつきません。人間が見ることができない地下水は地表水よりも脆弱で無防備なのです。 |
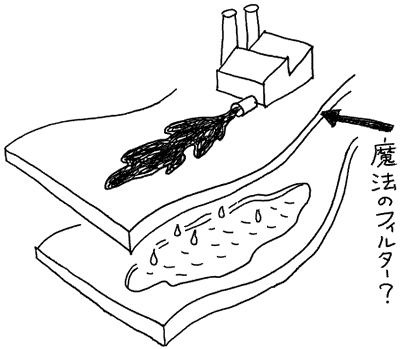 |
||||||
| 人間は危険な汚染物質をいまも様々な形で地下水に流し込んでいます。とりあえず目に見えなくして忘れるためなのでしょうか。途上世界の多くの地域で、いまだに工場が廃液を地上に垂れ流しています。地下に消えるのを待っているのです。先進国はそのようなことはないのでしょうか。 もうひとつ知っておかなければならないのは、費用的にも物理的にも浄化が困難であり、最も有効な対策は汚染の予防だということです。「地下水を吸い上げ、地上で汚染物質を除去・処理し、また水を地下に戻し汚染を薄める」というような技術で浄化が進められていますが、これには膨大な時間と費用がかかり、しかも汚染によっては浄化を選択することもできない帯水層もあるのです。その莫大な費用は当然、私たち市民が支払うことになります。ですから最初から汚染原因となる毒物を使用しないで済む経済活動を考える予防対策が最も有効であり、最も安上がりなのです。 「地球白書」では次のように提言しています。 |
|||||||
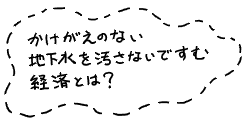 |
予防戦略をとるには、個々の工場やガソリンスタンド、トウモロコシ畑、ドライクリーニング施設などを調べるだけでなく、これらの経済活動の基礎となる社会、産業、農業の各システムのあり方に目を向ける必要がある。これらのシステムが生態学的に不適切であることが、世界の地下水汚染の元凶になっているのである。たとえば、世界中に広く見られる高投入型農業システムは、農業化学物質の大量散布によって農地 ― およびその下の地下水 ― を汚染する。また、拡張しつづける自動車中心型の都市システムは、石油化学物質、重金属、汚水で帯水層と土壌を汚染する。適切な対応をとるには、これらの各システムを注意深く総点検することが必要である。 | ||||||
|
Copyright (C)2001 Biwako
Shimin Kenkyusho all rights reserved
|
|