|
第23回
|
2002年1月17日 菱川貞義 |
| いのちを支える水<その2> 汚染予防が経済を支える |
地下水汚染に対して最も効果があるのが、“化学物質にあまり頼らなくて済むように農業の転換をはかる”ことのようです。例え農法の抜本的な転換が難しく、農薬を使うにしても、化学物質を大幅に減らすためのアプローチがいろいろ可能なようです。 |
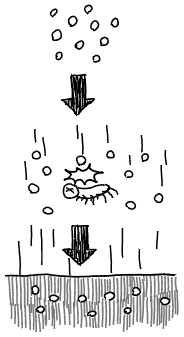 |
「地球白書」によれば、平均して使用される農薬のおよそ85〜90%は目標生物に到達せず、環境に放出されてしまうといいます。農薬を使うにしてもこれではあまりにもったいない。農薬が安いからこんな状況になるのでしょうか。例えばブラジルの果樹園では、1週間に1ヘクタール当たり約1万リットルの農薬が散布されているらしく、「散布方法を改良すれば10分の1の農薬で十分な効果が得られる」と専門家は指摘しています。農薬を良い悪いだけで見るのではなく、環境に悪影響を与えない使い方を模索することからはじめるのも、かなり効果がありそうです。 また、まったく汚染物質を出さない土壌改良法や病害虫防除法による農法なども注目されています。ペンシルベニア州のローデイル研究所によると、高度集約農法と伝統的有機農法を10年間にわたって比較したところ、汚染を予防するのはもちろん、有機農法が単収でも劣らないことが確認されています。「おいしいお米」研究に協力していただいている仲岸さんの不耕起栽培も、まさに化学物質に頼らない農法であり、しかも経済的にも十分に成り立つ農法を追及されています。 |
| もちろん農家だけでなく行政や企業の対応も大きな力となります。農家の農薬使用を抑制するため、インドネシアで毒性の強い農薬の使用を禁止し農薬補助金を撤廃したり、ヨーロッパ諸国で農薬や化学肥料に課税し大きな成果をあげています。またドイツの民間水道会社は、農家が農薬に頼らない農法をとるほうが経済的に利益がでることに気づき、そういう農法をとる農家に援助金を出しています。汚染された水から農薬を除去するより農家に投資するほうが安上がりだというわけです。 |
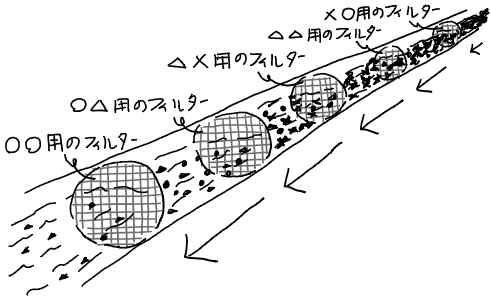 |
| これらの話は「地球白書」だけでなく、琵琶湖のまわりでもいろんな方が気づきはじめ、動きだしています。そういう人が10人、100人、いえ、きっと何万人といるはずです。ぼくは「そんな声を集めに行かなければならない」と強く感じています。何ができるか分からないけど、いまは、そうすることが大切だと感じるのです。 そして一人で聞くには「もったいない話」をみなさんと共有したいと思います。循環型社会とか、世の中のしくみや生活スタイルを変えるには“一人の個人”がまず自ら意識する、知識としてではなく意識して必要だと感じることがすべてのはじまりです。“思い”がなくては新しいことは何も生まれません。その強い意志をもった個人が一人、また一人と社会に存在していくことが確実に“変わるパワー”になります。 |
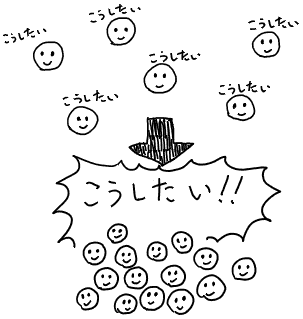 |
新しい意識の芽生えには新しい価値体験や学びが不可欠です。「農薬の消費を極力おさえることが地球のためだけでなく、お米の値段が高くても家計全体でみると経済的」というような気づきがあり、自分のために必要だと思える意志がしっかりあれば、こんな楽観的な見方が成り立ちそうです。 「同じ車に乗るにしても、どういう意識で乗っているかで、循環型社会の中で車も共生できるはずです。農薬にしてもきっと同じことだと思います。ナイフも!インターネットも!」 |
|||||
|
Copyright (C)2001 Biwako
Shimin Kenkyusho all rights reserved
|
|