西川嘉右衛門商店会長
| 西川嘉廣さん 西川嘉右衛門商店会長 |
|
|
| 第25回 |
大きく見ると、ヨシがヨシでなくなる?
|
| 2002年1月31日 菱川貞義 |
2001年も残すところわずか数日となった12月26日の西川邸での出来事。そこで行われた「環境とくらし」に関する密談(?)は、ここにおもしろく公表されることになった。 |
||||||||||||||
 |
最初に訪ねて来られた方は、(株)たねやの総務部エコロジー推進課の額田隆義さんです。 |
|||||||||||||
| 西川さん 「額田さんとびわこ市民研究所の菱川さんがここで出会えるというのはすばらしいことで、特に接点が2つあるんや。ひとつは農業のこと。『おいしいお米』の研究とつながっている。もうひとつは、たねやの山本社長。直々じゃないんやけど、ある人を介して、『ヨシの廬根(ロコン)の漢方薬を使ったようなお菓子を考えてみたい』と言われ、それに関する資料(中国の中薬大事典)を最近お渡ししたばっかりなんですよ。びわこ市民研究所でもヨシについての活用があるので。」 額田さん、ぜひ、びわこ市民研究所とつながってください! と言って早速、びわこ市民研究所のサイトの『おいしいお米』研究を見てもらいました。 額田さん 「これは仲岸さんですね。あっ、これは安井さん。この似顔絵いいですね。パッと見て分かりますねぇ。」 |
||||||||||||||
| とか言っている間に突然、額田さんの口調が真剣に。 「物質は人間中心の循環になるきらいがありますが、私は本来、自然の循環に学んで、自然の循環に近づけるべきだと思ってます。例えば、安いからといって海外の食料をどんどん輸入するのは環境にとってよくないことがいろいろでてくる。この前、宇根さん(農と自然の研究所代表理事)がおっしゃっていたように、農業も、食料をつくっているという経済だけじゃなく、気がついてなかった大きな意味での経済を考えないといけないんです。」 |
 |
|||||||||||||
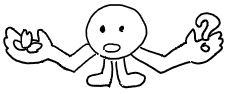 |
||||||||||||||
| 21世紀に入ってようやくみんながそのことに気づいてきたようで心強い感じがしています。気がつかない経済を考慮すると原発もずいぶん高くつきますが、最近では既存の経済でみても原発は高くつくということを推進派までが認めはじめていますね。 |
||||||||||||||
| 額田さん 「そうですね。」 西川さん 「はい、お菓子をどうぞ。額田さんもどうぞ。気がつきました?これ、たねやのお菓子です。自分とこのお菓子をこういうところでいただくのもおもしろいでしょ。たねやさんは全国有数のお菓子屋さんで有名。たねやさんのお菓子はすごく高いのに、この不況の中でも別格ですもんね。」 安全で栄養もいい食品だったら、食べるときは高くても、あとで病気になる危険が少なくなれば、そのほうが安くつくという考えもあるようですね。 |
||||||||||||||
額田さん 「まさに現代の日本の食生活はおかしいですね。医療費にかかっているお金は世界でも断トツです。飽食とか食生活が完全に乱れている。」 西川さん 「医食同源の知恵はどこかにいってしまった。」 額田さん 「宇根さんも言っておられたが、『何が生産かをもっと考えないといけない』と。いままでの生産はすごく限られた世界でしかない。すぐに役に立つものとかお金で測れるものとかそういうものでしょ。もっと大きな意味での生産は、自然から得られるもの、再生可能なもの、持続可能なものじゃないと社会の展望も開けないですよね。」 |
 |
|||||||||||||
環境のことが騒がれているわりには、大量生産してはじめて成り立つ経済ですよね、いまでも。 額田さん 「経済評論家に好きな人は少ないんですが、もと日経記者の内橋さんの話に共鳴しましてね。『大量生産、大量消費、大量廃棄の上に、日本はもうひとつ“短サイクル”がある、商品の寿命が短すぎる』と。ヨーロッパではタクシーでも古い車がいっぱい走っているが、日本はきれいな車ばっかり。日本は頻繁にモデルチェンジを重ねて、それで企業がもうかっている。なぜそんなことでもうけるのか。」 |
||||||||||||||
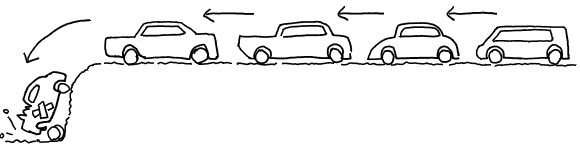 |
||||||||||||||
| いかに消費者に“飽きさせるか”という経済ですね。ひとつの車を通して企業と生活者がじっくりとつきあう経済みたいなものがあってもいいと思うんですが。 額田さん 「同じようなことで、ヨーロッパではカーシェアリングもすすんでいますね。」 平日に乗る人と土日に乗る人が1台の車を共有するといった生活スタイル。 |
||||||||||||||
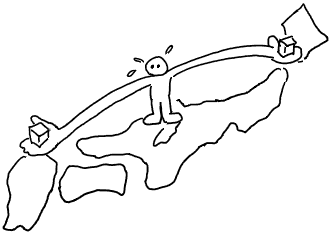 |
額田さん 「循環型といいながら私どもも、だんだんと商圏が広がって、広い地域に大量に販売、流通させるとなると、やっぱりいろいろ矛盾も出てきます。悩んでいるところです。本来、お菓子の原点といえば、パンなんかもそうですが、それぞれの地域にお店があって、その地域のものでつくるのが姿だと思います。パン、ハム、ソーセージとかが全国どこでも同じものが食べられる国は、おそらく日本だけでしょう。」 |
|||||||||||||
| 西川さん 「額田さんは世界湖沼会議でもりっぱな論文を発表されたんです。」 |
||||||||||||||
|
(次回につづく) |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 『声文』に寄せられた箋の中にもよく出てきた、大切な琵琶湖の資源のひとつである八幡川。その『八幡川流域を考える住民会議』が2000年9月23日に設立され、西川さんも構成委員のひとりとして活動されています。 設立趣意書にはこうあります。 私たちが住んでいる流域には、八幡川(堀)とその水源となっている北之庄沢、黒橋川(支川・三明川と平和川)といった川や沢があります。これらの川や沢は、私たちの暮らしになくてはならない水辺であり、雨水を安全に下流に流すだけでなく、農業、工業、家庭などからの排水を浄化しながら琵琶湖に流れています。また、それらの水辺は生き物をはぐくみ、観光和船の航路となるなど、多くの観光客が散策しています。 八幡堀は豊臣秀次が開削した内堀で、かつては近江商人の物資輸送の大動脈として栄えました。今では昔の姿を取り戻すために、水辺の清掃活動や美化活動など熱心な取り組みと、行政(県、市)による浚渫事業、浄化用導水事業などさまざまな努力が今日までなされてきています。 また、北之庄沢につきましても浚渫事業や岸辺の整備事業がおおむね完了し、美化活動なども始まり、活動の輪が上流にも広がりつつあります。私たちは、住民や企業と行政(県、市)が協働することにより、これらの水辺が、更に親しまれ、愛される河川環境の創造を目指していきたいと考えています。 このため、八幡川流域の住民が集まり、流域や川の現状と課題について議論するとともに、どのような環境を次代に引き継いでいきたいのか、そのために何をすべきか、それぞれがどのような役割を果たしていくべきか、などについて意見交換して、「流域環境宣言」、「維持管理計画」、「それぞれの役割」などを「八幡川環境保全計画書」としてとりまとめ、継続的な維持管理を進めていきたいと考えています。 |
||||||||||||||
 |
||||||||||||||
| この住民会議でも目指していることですが、知れば知るほど多様で生活に深くかかわっている自然は、みんなでよく見て、よく意見を交換し、よく考え、より多くの人々と行動することが大切なんですね。そうすれば「自然と合意が形成されていくのだろうな」と楽観的に考えてしまいます。 住民会議の提言などがどうまとまっていくのか楽しみです。 |
||||||||||||||
|
Copyright (C)2001 Biwako
Shimin Kenkyusho all rights reserved
|
|||