西川嘉右衛門商店会長
| 西川嘉廣さん 西川嘉右衛門商店会長 |
|
|
| 第27回 |
ヨシもアシもふみこえて
|
| 2002年2月14日 菱川貞義 |
| 不耕起の話に尾崎さんも興味を示したようです。 「不耕起農法というのは、具体的にどういうふうにやるんですか。」 額田さんは、とても分かりやすく不耕起農法を説明してくださいました。詳しい説明は「おいしいお米」研究のページを見てください。尾崎さんは、特に「苗を厳しく育てて病気に強いイネにして、農薬に頼らないようにする」という話に納得したようです。 |
||||||||||
 |
尾崎さん 「人間もあんまり甘やかすとよくないです。」 人間も、「薬よりまず病気に強い身体をつくらないとダメ」というのと同じですね。こうしていつも“環境”の話を聞いていると、特別 なことは何もなくて、よく考えてみたら当たり前のことばかりなんですね。 |
|||||||||
額田さんが不耕起の説明をしている間に大林環境技術研究所代表取締役の大林久さんが現れました。 |
||||||||||
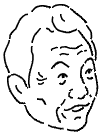 |
大林さん 「この前、西川さんとかとお会いしているときに、なんか今日、農業のことの話をやるって聞きまして、ちょっと用事の帰りに寄ってみたんです。」 |
|||||||||
| 西川さん 「今日の話は大林さんには言ってなかったのに、ぴったりこんなことになるなんて何でやろなと思ってたんです。」 大林さん 「実は私、農業は本業じゃなく、スギの皮で商いしてるんですけど、農家の次男坊ですから気になるんです。農業というのももうちょっと知恵をだしたら、もっと良くなるのにと思ってるもんですから。」 西川さん 「しかし、これは願ってもないメンバーが揃ったなぁ。いまも農薬の話をしていたんです。」 |
||||||||||
 |
||||||||||
|
|
||||||||||
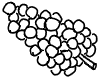 |
||||||||||
| 「でも種無しブドウは、武田でぼくが一番にやったんですよ。あれはタケノコの成分を使っているんです。」 西川さん 「要するに成長ホルモンなんですね…? あのジベレリンは大林さんがやらはったんですか?! 武田の農薬といったらあれが一番…。」 大林さん 「それで社長表彰もろたんですよ。一番やったからね。でも効果が半分しかでなくてマダラ模様のブドウになる事故がありまして、武田のジベレ事故といって。昭和40年に武田の農薬の売上が13億だったんですが、7億6200万円も保証をとられたんですよ。ぼくも神経太いほうなので、『何もやってないやつはそら事故も起こさんけど、やってたら事故も起こす』とか言ってたんですが。」 |
||||||||||
| 「その頃は朝飯を食う前に毎日まず新聞を見てたんです。活字になるというのは怖いですね。家にも何にも言うてませんでしたから、今日はご飯いらんちゅうて、すぐ記事が出てた新聞を会社に持っていきました。こんな大きな活字が出てました。だけどそんなとき…!?
失礼ですけど、こちらは女性の方ですか?」 尾崎さんは男性です…。 |
 |
|||||||||
| 西川さんほか 「ぐははははははははっ。」 大林さん 「いや、実はいま女性の話を…、食品を担当している女性がいまして、『大林さん、そんなん気にせんかっていいです。社長でも億という金なんか動かされへんのに、1人で10億ぐらいの仕事をしたと思ったらええよ。』と言ってくれるんです。山にいっしょに登ってた子なんです。」 西川さん 「そうやったなぁ、私もその記事は覚えてる。」 大林さん 「そうなんですか。」 西川さん 「実は私も種無しブドウで新聞に出たことがあるんや。」 大林さん 「そうだったんですか!先生。」 |
||||||||||
|
(次回につづく) |
||||||||||
|
|
||||||||||
| ヨシ博士のまわりは人と情報がてんこもりで、みんなおもしろいので最近大食いのしすぎで、はやく情報を消化して記事にしないと大変なことになりそうです。先日の2月11日(月・祝)のヨシ刈りイベントでも、またすごい人たちにお会いし、おもしろい話をいっぱい食べてきましたので次々レポートします。 |
||||||||||
 |
||||||||||
| 2月2日の読売新聞に以下のような記事が掲載されました。 刈り取ったヨシ利用、活用。県が新群落保全基本計画素案 1993年3月施行の現計画が、ヨシの植栽にこだわっていた点を生態系保全の視点から修正。維持管理のため刈り取ったヨシの利用、活用について、新たに項目を設けた。 特にヨシ群落保全の重要事項として「かつてヨシはあらゆる生活の場で利用、活用されていたが、その大部分が失われた。これらをもう一度見直すことが必要」とし、たい肥化や製紙のほか、新しいヨシ文化への積極的な支援を盛り込んでいる。 この記事を見せてくれた西川博士は、 「びわこ市民研究所ではじめようとしているヨシ商品開発プロジェクトや農業研究も、時代の要請の中で大いに期待できる。」 とおっしゃっていました。 ぼくたち普通の市民に「なにができるのか」という不安はありますが、何かきっと大切なことができるはずです。市民が市民の環境やくらしにかかわることをやるのですから。みなさんがんばりましょう。 |
||||||||||
|
Copyright (C)2001 Biwako
Shimin Kenkyusho all rights reserved
|
|||