西川嘉右衛門商店会長
| 西川嘉廣さん 西川嘉右衛門商店会長 |
|
|
|
| 第28回 |
あれもこれも・・・、ヨシ、もっと研究したい!
|
| 2002年2月21日 菱川貞義 |
 |
やっぱり、“研究”って、とても楽しいことみたいです。こんな話をしている西川さんたちの会話は熱を帯びる一方です。大林さんもいつまでも研究が好きなんですね。自分がつくった会社の名前が大林環境技術研究所というんですから。 |
||||||||||||||
| 西川さん 「糖脂質で種無しブドウをつくることができるんや。でもそれは商品にはならなかったんや。新聞には載ったけど。」 「ジベレリンが先発なんでしょ。それを大林さんが最初にやったとは初耳だった。」 大林さん 「花の咲く2週間前に処理せなあかんのがひじょうにむずかしい。ですが、使うのは1万分の1に薄めた液です。」 西川さん 「そんな薄い液で種無しブドウができるなんて不思議やなぁ。成長ホルモンでしかないのに。」 「ジベレリンはタケノコからとられたんですね。タケノコは竹やから、あれはイネ科の植物なんです。ヨシもイネなんですが、ヨシの成長ホルモンはジベレリンじゃないんですよ。」 |
|||||||||||||||
| 大林さん、額田さん 「えっ!?何なんですか?」 西川さん 「オーキシンなんです。でも、ジベレリンも見つかってないだけで、もっとよく研究すれば出てくるんじゃないかと思うんです。同じイネ科ですし。わずか4〜8月の数ヶ月の間にあれだけ成長するんだから。オーキシンにはそんな力はないと思うよ。ゼロから4mも4ヶ月で伸びるのは相当なパワーです。竹よりずっと速いです。」 |
 |
||||||||||||||
| 大林さん 「そう言われたらそうなんですね。で、この前そんな話を先生からお聞きしまして、こんな袋を持ってきたんですよ。ヨシも、やればまだすごいことが眠っていると思って。研究に値するなと思って、ちょっといただいて帰ろうと思いまして。」 |
|||||||||||||||
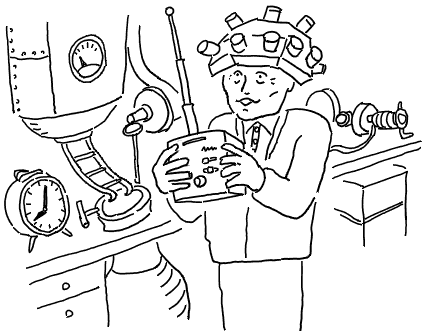 |
|||||||||||||||
| 大林さんがヨシの研究をするなんて、ちょっと楽しみが増えました。いったいどんなことになるのか。とてつもなくびっくりするような発見があるような気がします。大林さんの研究所にも行ってみたい。映画『バック・ツー・ザ・フューチャー』のドク博士の研究室を勝手に想像しちゃいました。 西川さん 「大林さん、沖縄の話をしてください。」 大林さん 「あ、沖縄。自然の力はすごいんです。ちょっと人間がいじると沖縄が大変なことになってて…。」 「あそこは山が赤土で、道路とか何とかをつくって地肌が出てきて。それが、止めどなく雨が降りますと、ざーっと海に流れでてしまう。それで『サンゴが死ぬ』っていうて環境団体から訴えられて裁判になってるんです。で、誰が止めようとしてもほんまにダメで…。」 自然のバランスはひじょうにもろいんですね。それに一度くずれるとなかなか元にもどらない。 |
|||||||||||||||
| 「実は私、沖縄には行ったことがなかったんです。『来てくれ』て言われて、その時は台風シーズンで、もうほんとに海がピンクみたいに染まってるんです。3日から5日ぐらいは浮遊してて、それがずーっとサンゴにおりてきて、沈着するというか、サンゴが死ぬんです。そこを芝を植えて土が流れないようにするんです。で、『やれ』て言われて、上から下までやったんです。急な斜面は、普通ネットをして吹きつけてやるんですけど、我々はネットなしでやります。我々のつくった一角だけが芝生のじゅうたんになってますからね、ひと目見たら分かりますよ。急なところをやっても、うちだけがきれいに芝生がつくんです。」 |
|||||||||||||||
 |
|||||||||||||||
| 「いい芝かどうか一目で見極め、知恵をもうちょっと使って…。でも、いままで私の芝生は誰も相手にせんかったんですが、アヤハの社長が参議院で環境部会の副部会長か何かをしていて、『環境にいい仕事は新規事業としてやれ』と言ってくれてて。それぐらいではなかなか商売にはならんですけど。」 西川さん 「淡海環境保全財団がつくってるヨシの腐葉土も、実はアヤハで売ってるんですよ。」 なんか、アヤハも環境に何かこだわりがありそうですね。 大林さん 「西川ふとん店の場所を借りて、知事さんの新世紀を語る会というのに出たんです。そこで、みなさんが農業はアカン、アカンて言うておられたんで、『私は技術屋だから、先の話はできないけれど、目前のやつはできる、すぐできることがいっぱい考えられる』『農業も知識を出さずしてアカンアカンなんて言う前に、京阪神に近いし、グルメだとか、新鮮だとか、安全だとか、切り口がいろいろあるのに、何でもかんでも中国や韓国に負けるなんて言うとらんと、もうちっとやれば、ぼくは専門やないけど、何かあるはずや!』」 ほんとうにアカンのなら、やめてしまうしかないけど、“いいもの”をもってるのならやり方はあるはずなんですね。 |
|||||||||||||||
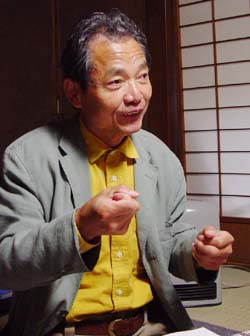 |
「ぼくも『スギ、ヒノキの皮は使えない、ゴミだから燃やすしかない』と言われていたのを、有効利用できるようにしたんです。スギ・ヒノキの皮は役に立つんです! いまはスギ・ヒノキの皮だけで飯を食ってるんです。スギ・ヒノキの皮は十分すごいんです。西川さんと同じでひとつしかしてないんです。人真似じゃなく、私がはじめにこれはいいと言って、信じて…。」 西川さん 「でも、信じがたい効果があるんだよね!」 |
||||||||||||||
| 大林さん 「私は菌は専門じゃないので、スギ・ヒノキの皮の機能を2万3000個いる菌から測ってもらったんですよ。ほっといたら1日で620万個に増えるんですよ。300倍ぐらい。それがスギの皮を入れたら、逆に1000ぐらいに減って、最終的に20個ぐらいになるんです! 効果がずっと続くんです。」 |
|||||||||||||||
| 西川さん 「大林さん、これおひとつどうぞ。これは黄色ブドウ状球菌も亜ヒ酸もなんにも入っていない上等のお菓子なんです。」 大林さん 「たねやさんのお菓子はなかなか家では頂けないんで、頂戴します。」 |
 |
||||||||||||||
| 額田さん 「わたしが言うのもなんですが、どうぞ。」 西川さん、いいタイミングですね。ちょっと興奮してきた会話に一息いれましょう。 |
|||||||||||||||
|
(次回につづく) |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2月11日(月・祝)の「西の湖宝探し」のイベントで、盛りだくさんの楽しいプログラムに交じって、西の湖美術館づくりとヨシ舟づくりのキックオフ宣言がありました。 環境改善と景観の美化をすすめるために行われる、西の湖を美術館に見立てた「西の湖美術館づくり」の原案は次のようなものです。 |
|||||||||||||||
 |
|||||||||||||||
| 1) 入口にヨシで作った大きな「茅の輪」のゲートを作ります。 2) 会員のボランティアが先ず回廊の整備をはじめます。次いで他のボランティアの方や、地域のみなさんに呼びかけて整備を進めます。 3) 企業や行政の方の参加を呼びかけてさらに回廊計画の完成を目指します。 4) 皆で整備作業を進める中で、特に美しい、好ましい環境、景観スポットを話し合い決めていきます。 5) ヨシ刈りボランティア発祥の地を正面入口とし、そこから時計回りで、決めたスポットに番号をつけます。その番号が美術館のルーム番号となります。 6) ルーム番号は看板に表示し、看板にそこに見える景観の特長(水、植生、野鳥などの)や協力依頼事項を記します。 7) この美術館は副会長の西川嘉廣さんが創設されたヨシ博物館とリンクします。 8)回廊は自然任せにするのではありません。自然と人の手の調和により、里山のような心休まる「里のヨシ原」づくりを目指します。 |
|||||||||||||||
|
Copyright (C)2001 Biwako
Shimin Kenkyusho all rights reserved
|
|||