西川嘉右衛門商店会長
| 西川嘉廣さん 西川嘉右衛門商店会長 |
|
|
|
| 第29回 |
感じるからこそ、ヨシ!と確信する
|
| 2002年2月28日 菱川貞義 |
| 大林さんの独創性や強い信念はどこからやってくるんでしょうか? 額田さん 「なんで気がつかれたんですか? スギの皮にそんな効能があるのを。」 大林さん 「通産省が石油の消費をなんとか減らそうとしたんですよ。その中で無駄遣いをしてるところはないかと言ってね。そんな話を聞いて、スギの皮はスギを守っているんだから、いろいろ役立つことがあるはずだと思ってやってたら…。学校やゴルフ場の土に埋めて、農薬を使わずに除菌できるんです。スギは天然のもんですから、魚とかは死なず、菌だけを殺すんです。線虫までは殺すんです。」 |
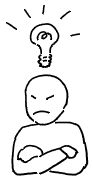 |
||||||||||||
| 「それで効能が分かると、岩手大学が興味を示して、共同研究しようと。あそこは成分を抽出してやるって言うんですよ。ぼくはそれはやらないって言ったんです。なぜかというと、繊維構造のためなんです。」 「いままでの堆肥だったらくさっていって、ペタッとなるでしょ。芝生でも何でも根で呼吸しとるから、土の中にすき間ができなあかんのです。芝生を踏むと成長が悪くなるのはこのためなんです。それがひとつと、土の中に繊維構造を入れるというのが大事なんです。」 |
|||||||||||||
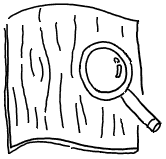 |
|||||||||||||
| 西川さん 「成分を抽出してしまったら、その意味がなくなってしまうんですね。」 大林さん 「そうなんです。岩手大学は3年で開発するって言ってますが、ムリだと思います。抽出するとなると簡単なものでも毒性実験に何億とかかるんです。そして5年とかかけて。『なぜ天然物ですら、一般の合成と同じように毒性実験せんならんねや』ともいわれるんですが、法律でそうなってて。でも天然物ですから、ものすごくいっぱい成分が含まれているんです。そのひとつひとつを測っていたら、もうぜんぜん…。」 西川さん 「薬も同じやけど、ひとつの成分というより、複合の効果というのが重要なんだが、これはもう無数の組み合わせができてしまう。だから研究というのはひじょうにむずかしい。特に漢方というのは、生薬だけでも何種類か混ぜるでしょ。単独の生薬にもいっぱい成分がある。だから、どれがどう効くというのを突き止めるのは大変なんですよ。」 |
|||||||||||||
 |
|||||||||||||
| 大林さん 「もうひとつは代謝物といって、人の身体に入って分解したのが毒性があるかどうかも、いまは見なあかんのですよ。だからいま薬を出そうと思うと…。」 西川さん 「武田が新薬を出そうと思ったら、いまだったら最低100億はかかるでしょうね。」 大林さん 「それで10年間…。」 |
|||||||||||||
| 西川さん 「ちょっとでも毒性が出たら、お金をドブに捨てたことになる。」 大林さん 「ちょっと発ガン性が見つかったらもう…」 |
|||||||||||||
| 西川さん 「ここが問題なんです。ついには効かなくてもええから、副作用がないほうがエエということになる。効かないものを薬事審議会の目をうまくごまかして通すことに力をいれる。どんなにいい効果があっても、1万人の中で9999人がその薬で治っても、1人に副作用があったらその薬は出せないんですよ。」 大林さん 「しかも自然界で一番弱いバクテリアとかカビでちょっと変異性があったら、それも問題になる。ネズミならまだ人間に近いんですけど、カビみたいなのはちょっと何かあると…。」 |
|||||||||||||
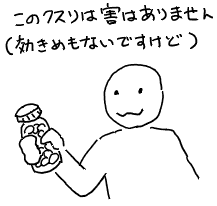 |
|||||||||||||
| 西川さん 「あっという間に突然変異が起こる!」 もし、いままでの薬では効かなかったのに、1万人のうち9999人に効く薬があったら、生活者に審議させればりっぱに薬として世に出ますよね。『1人にこんな副作用の出る可能性のある薬ですけど』という、但し書き付きで。 |
|||||||||||||
 |
|||||||||||||
|
(次回につづく) |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 東近江水環境自治協議会が中心になって、2月より西の湖美術館をつくる取り組みがはじまっています。西の湖美術館への“思い”が、美術館の案内図にありましたので紹介します。 |
|||||||||||||
 |
|||||||||||||
| 西の湖美術館 西の湖の水をきれいにしたい。西の湖のヨシを守り育てたい。昔のように、水に飛び込んだり、水辺で子供たちと遊びたい。……… どうしたらいいのだろう。 西の湖の風景は、何時見ても、いつまで見ていても、見あきる事はない。 八幡山に沈む夕日。安土山の上に登る秋の月、ヨシの鳴る音、風の音、三角形に立てられてヨシ、春風にほのかにゆれるヨシの新芽、みんな、みんな、ナミダが出る程、美しい。 すがすがしいまでに美しい西の湖。自然が創り出す美しい風景の一瞬、人間が作り出すものでは、どんなにガンバっても勝てない。 人間が作り出せないほどの美しい場所、それはもはや人間のものではなく、神のもの、それは聖域。 犯してはならない所、汚してはならない場所として、人間世界との結界を張って守ろう。そして、そのエリアを美術館、西の湖美術館と呼ぼう。 日本庭園の技術には借景という部分もある。西の湖の岸辺に立った人、水郷をめぐる人、西の湖の景色を見る人。それぞれが美しいと感じ、切り取った風景、それが西の湖美術館の展示作品。 展示作品を、そこに来た人が見つけだす美術館。そんな美術館があってもいいのではないか。 それが『西の湖美術館』です。 |
|||||||||||||
|
Copyright (C)2001 Biwako
Shimin Kenkyusho all rights reserved
|
|||