西川嘉右衛門商店会長
| 西川嘉廣さん 西川嘉右衛門商店会長 |
|
|
|
| 第30回 |
“ヨシ”と言えば“アシ”と言う
|
| 2002年3月7日 菱川貞義 |
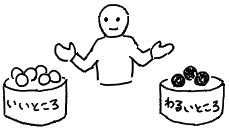 |
病気に効くとか副作用とかの話を聞いていると「何が安全なのか」という評価はむずかしい問題ですね。 額田さん 「いまは、最終的にリスク評価をしていかざるを得ないと、かなり言われてきてますよね。まったく安全なものはないことが分かっている。自然の毒性もあるし、ごまかすのではなく、除けない危険性もきちんと評価する。」 |
|||||||||
| 西川さん 「いまの現代科学では、評価は動物実験なんです。もちろん動物実験に使った結果と人間に対する結果は必ずしも一致しない。だから動物実験のあと、ボランティア的な人間を対象にしてから薬になるんだけど。でも漢方のいいところは動物実験はないんです。何千年の歴史の人体実験があるんです。そして、効かなければ、何千年も人間が重宝するわけが、そんなバカなことはないんです。何千年の人体実験を経てるのが現在に残っている。その中でヨシの廬根(ロコン)もこれだけの効能があるということなんです。」 額田さん 「そういえば食べ物もそうですね。かなり昔からいろんな人が毒きのこを食べて死んだり…」 西川さん 「そうしていまの食べ物が残っているわけです。フグ中毒もそうです。身体に悪いもの良いものが長い歴史の人体実験で分かってきた。同じく漢方はそこがすごいんです。」 |
||||||||||
| 額田さん 「そうしてみると昔から“医食同源”というように、食べ物と薬の境目というのは、あんまりないですよね。」 西川さん 「なくて当たり前でね、これは食べ物、これは薬というようにわけるのは西洋医学です。だけど、食べ物がいくら健康的でも『たねやさんのお菓子はまずいよ』となったら売れないでしょうけど。」 |
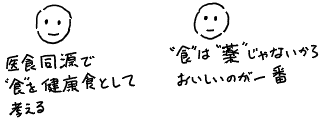 |
|||||||||
| 医食同源を考えると、食べ物に気を使っていればあまり薬に頼らなくてもよさそうですね。逆に食べ物は安けりゃいいとかいって、薬代が高くついていたら何にもならない。多少高くても健康にいい食べ物を食べたほうが結果的に安くつくかもしれないですね。 西川さん 「大林さんは、ひじょうにオリジナリティのある研究をされてて。しかもちゃんと成果がでてるのが不思議な感じ。この業界は成果がゼロでも普通なんや。」 |
||||||||||
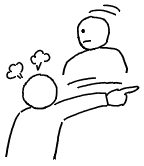 |
大林さん 「『なんで君は…』とよう言われることがあるんです。50人、60人が集まった会議でものが決まるんですけど、みんなが『これはええ』て言うたのは、ぼくは全然やらなかったんです。誰かがええて言うたら、考えも無しにみんな目がそこにいっとるのを見てて、だから、みんながこれはアカンて言ってたら『これはほんまにアカンのか』て思う習性がいつの間にかついてしまったんです。」 |
|||||||||
| 「ただ、あまのじゃくで反対してるんじゃないんです。ぼくはやっぱり近江商人の血を多少ひいとるからね、ほんまに左へ行ったら勝ち目がないのかちゃんと見てるんです。こういうふうに左へ行ったらアカンけど、こうして行けば勝ち目があると見てから左へ行ってるんですよ。でも、普通の人間に言わすと、あいつはあまのじゃくだから、人が右と言えば左へ行くんだと言うんですよ。だけどぼくは、ぼくなりに計算してるんです。」 |
||||||||||
| 「それで武田にいた最後のほうで、小さな研究所の所長をやっておったとき、本社から『こんなおもしろい記事が新聞に出たからやれ』と、FAXでだーっと送ってきたんです。ぼくは『新聞に出たものはやらない、そのまま捨てろ』って言ったんです。よく言うんですけど、少なくとも自分と同じ考えは3000人はおると思わなアカン、会議をして『これいいからやりましょ』なんて決めたことは誰でも考えてることや。その中で生き抜こうと思ったら、みんなが言ったことにすぐハイハイって聞くなと、若い人には言うんです。」 |
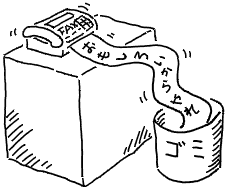 |
|||||||||
| 大林さんの話を聞いてると、ヨシも「活用がむずかしい」なんていわれているけど人の言っていることなんか気にしないで、がんばってやれば何か生まれる気がしてきますね。 額田さん 「私、次がありますのでこれで失礼します。びわこふるさとオーナー会の会長の岡田さんもおもしろいんです。本業は麻なんでが、麻もまたヨシとちがっておもしろいんです。会ってください。」 |
||||||||||
 |
西川さん 「伴ピーアールでは麻とヨシで新しい繊維を作っているんや。」 額田さん 「麻というのは奥が深いんです。」 西川さん 「この辺の特産なんです。近江商人は麻で大きくなったんです。」 |
|||||||||
| 額田さん 「本来はどこでもとれたんですけど、いまは許可制なんです。」 西川さん 「“たねや”さんも名前の通り、元々は農業に関係があるんです。」 大林さん 「“たねや”さんて、昔は漢字でしたね。」 額田さん 「そうです。」 西川さん 「漢字だとタキイの種みたいになって、“お菓子”を売っているのが“おかしい”ことになる。」 でた! 額田さん 「すいません。本当にこれで。」 額田さん、今日はありがとうございました。 |
||||||||||
|
(次回につづく)
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ヨシの化学的応用にはどのようなものがあるのでしょうか。西川さんの論文「ヨシと人の暮らしとの係わり」から世界の研究概要を紹介します。 アメリカ化学会発行の「Chemical Abstracts」(以下「CA」と略記)のVol.36(1942)〜Vol.129(1998)につき、“Phragmites”および“reed”をキーワードとして検索したところ、総計1124報(うちReviewは23報、Patentは89報)が得られた。これら報告を発表国別にみると、旧ソ連182報、ルーマニア158報、旧西ドイツ98報、中国79報、米国67報、日本67報、英国64報、韓国・北朝鮮33報、フランス27報、ハンガリー25報、オランダ23報、旧チェコスロバキア21報、オーストリア20報、カナダ19報、ポーランド19報、エジプト15報、オーストラリア15報、スウェーデン14報、デンマーク14報、インド13報、スイス11報(以下略)の順になる。 また、これらの報告を研究領域によって分類すると、<製紙>410報、<水質浄化>403報、<植物化学・植物生理学>301報、<成分>190報、<建材>37報、<飼料>36報、<発酵>20報、<燃料>15報、<生理活性・医学>13報、<活性炭>5報、<掘削>2報、<肥料>2報、<染料>2報、<吸着剤>1報、<滑剤>1報となる(複数領域にまたがる報告がある)。 (西川さんの論文「ヨシと人の暮らしとの係わり」からの情報) |
||||||||||
|
Copyright (C)2001 Biwako
Shimin Kenkyusho all rights reserved
|
|||