西川嘉右衛門商店会長
| 西川嘉廣さん 西川嘉右衛門商店会長 |
|
|
|
| 第35回 |
栽培してもヨシ!といってあげたい |
| 2002年4月11日 菱川貞義 |
| 西川さん 「ヨシもいろいろ考えられていて、ヨシを炭化させて活用しようと研究している方もおられる。麻の話も伺っていると生活用品などに活用できそうだが、麻は高価なイメージがある。」 岡田さん 「繊維で見ると高価なんです。でも素材そのものから出発するとまったくちがうんです。」 「いま一番の問題は日本で採れないということなんです。禁止されてますので。海外へ行かなならんようになってしまったんです。」 |
|||||||||||||
| 西川さん 「大麻があるから…」 岡田さん 「法律がありますから、産業化はムリでしょうね。趣味として残ることはできると思います。麻を産業化できることが必要やと思うんですけど。法律があってむずかしい。」 |
 |
||||||||||||
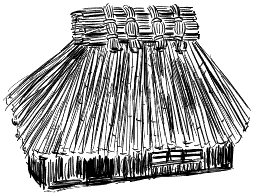 |
西川さん 「ヨシの屋根も同じです。火災になるというので、建築基準法でつくることができない。」 岡田さん 「今度、この目で原産地を見に行こうと思ってるんです。」 |
||||||||||||
| 西川さん 「麻は本来、暑いところがいいんじゃないですか。」 岡田さん 「麻はだいたい25種類ぐらいあるんですよ。その中に寒い地方でできるものと暑い地方でできるものとあるんです。」 |
 |
||||||||||||
 |
西川さん 「織物としてはどっちが上質なんですか?」 岡田さん 「両方とも上質です。ロシアでもできるんです。」 西川さん 「麻薬成分があるのは全部じゃないですよね。」 岡田さん 「インドあたりの大麻が強いです。」 |
||||||||||||
| 西川さん 「それなのにすべての麻を許可しないんですか?」 岡田さん 「そうです。でも日本の麻は若干、麻薬成分があったんでしょうね。だけど、いろいろ研究がされていて、昔はこの成分は癒しの効果として使われていたというんです。病気を直したり、精神安定剤として使われたり、日本の麻は心を癒す効果はあっても、幻覚作用ほどの強いものではないらしいです。」 |
|||||||||||||
| 西川さん 「幻覚作用だったら、ヨシだってね。あれは麦角(バッカク)菌が寄生すると強烈な幻覚作用があるんです。でも医薬品になるんです、重要な。麦角菌はふつう、字の通り麦に寄生するんですが。でも、すべて許可しないなんて納得できないね。」 |
 |
||||||||||||
| 岡田さん 「そうでしょ。ここ湖東地区は“麻の産地”といわれてまして、昔はいたるところで栽培されていたと聞いてます。」 西川さん 「主に蚊帳を作っていたんですよね。」 岡田さん 「中世の頃は麻の栽培地としてマークされているぐらいだったんです。たぶんここで織られたものは、京都の公家さんの着物とか、大麻の良い軸はお箸などに使われていたようです。それが戦争が終わって、全部、栽培を禁止されたんです。」 「麻はすごく用途があったんです! 上質の油がとれたんです! 麻の実から。油もとれるし食料もとれたんです。麻については日本独特の産業があったんですが、それを全部やめることによって、石油の消費とか、工業化を急速に進めるために、自然から栽培してうまく循環していたサイクルを全部やめてしまったんです。」 まったく知りませんでした。とてもかなしいことですね。 だれにお願いすればいいんでしょうか、「実はこんなにいいものだから栽培させてほしい」と。 |
|||||||||||||
 |
岡田さん 「いま環境の時代になって、地域の需要と地域の供給が見直されてきていますが、戦後、大量生産、大量消費をやったために地域の流通が無くなってしまった。地域で細々と自給自足してきた文化をすべて法律によって抹殺された。戦争で失ったものは人命とか建物だけじゃなくて、日本独特の文化そのものも…。日本の文化とか営みといったものを。」 |
||||||||||||
| 自分がもっていたいい文化を自分でずーっと無視してきて、それで欧米の文化をどんどん取り入れて、欧米と同じように環境が破壊され、ゴミがどんどん増えて、捨てるところが無くなって、水が汚染されて飲めなくなってきて、やっと日本文化の良さに気づいたんですね。 「やっと気づいたんです! で、麻というのは本当にこのへんの地場には最適な草なんです。日本の麻の文化がどれほど有益なものか知ってほしいんです。」 |
|||||||||||||
|
(次回につづく)
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 「ヨシと童話」 | |||||||||||||
 |
2002年2月24日(日)午後に西川邸で「ヨシと童話」をテーマにヨシ文化懇話会が催され、ぼくもはじめておじゃまさせていただきました。たくさんの方が集まっておられてびっくり。 岡田さんのほうでもこの時間に酒遊館というところで、7月に予定している麻をテーマにしたイベントの会合があったのですが…。 |
||||||||||||
| あれ、岡田さん?? 岡田さん、自分の会合があっちであるのにこっちに顔を出している!? 岡田さん 「いや、すぐ失礼します。麻の会合に出ないといけないので。」 西川さん 「えっ、“麻”は“朝”で終わったんでしょ。」 岡田さん 「いえいえ、昼からです。」 |
|||||||||||||
 |
|||||||||||||
| ともかく、ヨシにかかわるたくさんの童話やヨシカルタや伴ピーアールの社長夫人の創作童話などたくさんの話を聞きましたが、特に西川さんの次の言葉はじんと残りました。 「環境教育や総合教育も教育しようとすればするほど教育にならないのではないか。子どもは自然を相手に遊ぶだけで自然のことを十分学べるはずだ。身体で覚えたことはすぐに答えとしてでなくても、あとで効いてくるものだ。」 「童話にしても、これこれに注意して生きなさいと直接言わないけど、なにげないストーリーの中で気づくところがちゃんとある。子どもはそれを感じることができる。童話をもっと環境教育に役立てるべきじゃないか。」 |
|||||||||||||
|
Copyright (C)2001 Biwako
Shimin Kenkyusho all rights reserved
|
|||