西川嘉右衛門商店会長
| 西川嘉廣さん 西川嘉右衛門商店会長 |
|
|
|
| 第37回 |
“思い”をつないで、なかヨシに |
| 2002年4月25日 菱川貞義 |
| いろんな方とお会いしていると、みなさん共通して大切にしているコトに気がつきました。「もっと自然やいのちとかかわろう」ということ。ヨシ原も、田んぼも、川も、湖も、かかわらないで、生活と切り離しては守っていけない…。 |
||||||||||||||||
 |
岡田さん 「かかわらないで守るのはムリです。実は滋賀県の環境総合計画、これが今年から見直されることになっています。過去“マザーレイク”というような計画が立ち上がりましてね、徐々にここまで来たわけですが、ここら辺りでいっぺん見直さなアカンと。住民と企業と大学関係で人選されたんです。」 |
|||||||||||||||
| 「わたしは一応、住民というカタチで、NGOとして参加させていただいてまして、第1回の会議があったとこなんですが。そこでわたしが言ったことは、まさにそのことで、『もっとくらしが見えていくような環境対策をとらないとアカン』と。ただ自然のデータとかそんなものを見るのじゃなくて、人間がかかわっていくようななかで環境対策をしていく。自然を守ろうとするだけじゃなく、自然とかかわろうとする環境づくりが必要だと思います。」 |
||||||||||||||||
| 「ひとことで言うと“里山”という対策があるんです。あれは山の方ばっかり向いている。そうじゃなくて、もっと街中にある里山づくりを、もっと真剣に考えなきゃいけないんじゃないですかと提言しているんです。大津の川も釣りができなアカンと思いますし、ビルとビルの間にも空き地や田んぼがあります。そこをもっとみんなで環境にいいようにしようと。そうすると気持ちも変わっていくというようなお話をさせていただいてたんです。」 |
||||||||||||||||
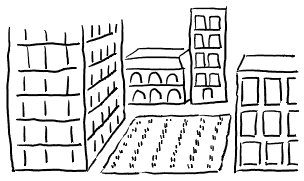 |
||||||||||||||||
| 釣りをする人の中にも、当然環境のことを考え、釣り糸やワームを自然に残さないようにとか考えていて、そういう人たちの中には、漁師さんとかと敵対するんじゃなく、いっしょに協力して、自然にかかわっている者同士として環境のことを考えられないだろうかと思っている人もいるんです。残念ながら、そういう漁師さんとつながる方法をもっていないんです。 |
||||||||||||||||
| 岡田さん 「いやあ!!それ!実はね!いまは田んぼなんですけど、この『ふるさとオーナー会』の前に、わたし、『自然な暮らしクラブ』を立ち上げたんですけど、半年くらいでポシャりましてね。それはあまりにも範囲が広すぎてうまくいかなかったんですよ。あの時の会のメンバーの思いは『漁師さんとわれわれとつながりを持て』。それで沖島まで行ったんです。漁業で生計を立てておられる人がいて。」 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
| 「そしてバージョン2が、いまの“ふるさととつながる”なんです。これがなぜ成功しているかというと、やはりメンバーの中に専業農家さんが入っていただいているのが大きい。足下を固められた。しっかりと。何か実現するときに、“思い”はいっぱいあると思うんですよ。漁業とわれわれの関係も、まず漁師さんの中でまとまって活動するのが大切だと思います。思いと思いがつながるとき、やっぱり一方的に思いを伝えるのではうまくいかない。だから、漁師さんの中に『環境のことを何とかせなアカン』という人がいたら、その人とタイアップしていきたい。」 |
||||||||||||||||
| 「“思い”はみんなある! でもなかなか実現できないでしょ。ズレがある。」 思いと思いがしっかりつながっていない、お互いの思いが共有できていないということでしょうか? |
 |
|||||||||||||||
| 「どうやら、うまくいかないのは、その辺に原因がありそうです。一方通行なんです。」 西川さん 「岡田さんとは東近江を通じて、たまたま知り合っただけなんだけど、ぼくは漁業の方はだれも知らないんですよ。ぼくがかつて知っている漁師さんといえば奥田さんなんやが。語りべ的な人。高齢で現役ではないんですが。」 |
||||||||||||||||
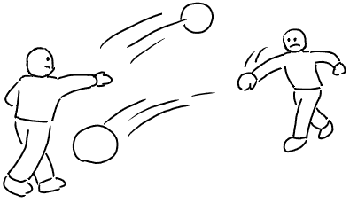 |
||||||||||||||||
| 岡田さん 「わたし、実は沖島に注目してるんですよ。あんなに身近にある島なんですが、生活空間がこことまるでちがうんです。沖島はエコアイランドができないかという構想を持っていたんですよ。いっぺん行くといいです。おもしろいです。クルマはないですが、ちゃんと生活の場があって、ほとんどが漁業ですね。」 |
 |
|||||||||||||||
 |
西川さん 「琵琶湖で住民がいる島っていうのは沖島が唯一なんです。ほかにいくつか島があるが、住んでいるのはここだけなんです。」 岡田さん 「日本でもこんな島は少ないでしょうね。」 |
|||||||||||||||
| 西川さん 「湖にある島ではないでしょうね。」 今日のお話のように、“強い思い”を聞くたびに、みんなの思いがちがうといっても大きなゴールは同じなので、環境のことをもっと仲良く進められないかなと思うんです。 |
||||||||||||||||
| 岡田さん 「根気よく続ければ、つながりもどんどんできていくと思う。ただひとつ思うのは、ボランティアではアカン、イベントではアカンということ。」 西川さん 「そうそう! 日本人はボランティアを無給奉仕と思っているけど、決してそうじゃない。」 |
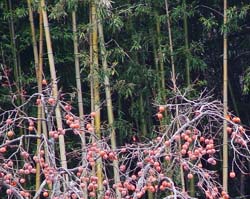 |
|||||||||||||||
| びわこ市民研究所も、もし価値のあることをやっているんだったら食べていけるはずだから、自立しようというのもひとつの目標なんです。 岡田さん 「“自立”はキーワードですね。自立となると活動自身に責任が出てくるし。とてもいいんじゃないですかね。お祭りではない、イベントではない、ということを明確にしながらこういう活動を続けていくのが必要だと思います。」 西川さん 「花火を上げることもそれなりの意味はあるけど、一番大事なのは地道に、ゆっくりでも持続することが大事だし、それにはやっぱり、言葉は悪いけど、稼げないと。」 |
||||||||||||||||
 |
市民参加イベントとかいった派手な催しも、多くは市民にとって実としては残らなくて、イベントを仕掛けたプロデューサーだけが目立って残るんじゃ何にもならないです。 西川さん 「イベントが目的になってるとダメです。いっときだけになってしまう。イベントから入るとどうしても続かない。」 |
|||||||||||||||
|
(次回につづく) |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 「びわ湖開き・ヨシたいまつを船から見る」イベント が2002年3月9日(土)にありました。 |
||||||||||||||||
 |
延べ3kmの湖辺に並べられた約600本のヨシたいまつがいっせいに点火されました。 大津市環境保全課の鳥飼さんのお話では、このたいまつは、多くの市民が参加した「市民ヨシ刈り」などで刈り取られたヨシでつくられており、琵琶湖の水質浄化・ヨシ帯保全を願い、琵琶湖の恵みに感謝する気持ちが込められているそうです。 |
|||||||||||||||
 |
びわ湖汽船・ビアンカでは、ミニ講演会と、コカリナとヨシ笛の演奏会がありました。 ミニ講演会は「ヨシと琵琶湖の環境保全について」と題した、ヨシ博士のお話です。西川さんは「ヨシについていろんな方の力を合わせたい」とメッセージされました。 |
|||||||||||||||
 |
「ヨシはたいまつやスダレや衝立などいろんなものに利用されていました。ヨシたいまつは昔は情報の伝達手段として使われていました。合図、信号として、のろしとして。そしていまは現代のくらしにあったヨシの利用方法が求められている。ヨシを守ったり、育てたり、活用したりするためには、いろんな方と取り組まないといけないと思う。行政もがんばっている。多くの住民団体も行政と力を合わせてやろうとしている。さらにいろんな方と広く手を組んでやっていく必要がある。」 |
|||||||||||||||
|
Copyright (C)2001 Biwako
Shimin Kenkyusho all rights reserved
|
|||