西川嘉右衛門商店会長
| 西川嘉廣さん 西川嘉右衛門商店会長 |
|
|
|
| 第38回 |
“いのちにヨシ”のくらしを求めて! |
| 2002年5月2日 菱川貞義 |
| 岡田さんの麻の話は衝撃的でした。そしてよく知ることができた麻は、ぼくの中でとても魅力的なものに変身しました。また、岡田さん自身の魅力にもふれることができ、得した気分です。岡田さんには今後もびわこ市民研究所といろいろかかわっていただけそうです。これからの活動が楽しみですし、その情報はびわこ市民研究所でも発表していただこうと思っています。 |
|||||||||
 |
魅力ある人物といえば、1年以上も前にヨシ博士の西川さんのところへおじゃまするようになってすぐに、ある人物の名前をよく耳にするようになりました。東近江水環境自治協議会会長の丹波道明さんです。西川さんからだけではなく、ほかの方からも「お会いしたほうがいい」と言われていました。 |
||||||||
| ぼく自身、去年の夏に環境をテーマにした狂言を観に行ったとき、丹波さんの舞台挨拶を直に聞いたことがあり、その時の「わたしたちは“いのち”をテーマに活動しています」というスピーチにひどく感動したのを忘れられないでいました。 あれからはやく会いたいと思っていながら半年以上も経って、ようやくその機会が訪れたのです。想像していたとおり、いや想像以上にステキな方でした。 エネルギーの塊というか、信念の塊のような、西川さんとはじめてお会いした時もそうでしたが、「若い!」と思いました。西川商店にあるヨシ商品を見せてもらいに行った2002年2月4日(月)、西川さんが丹波さんを招いてくださってました。 |
|||||||||
| 丹波さん 「これが東近江水環境自治協議会設立の経緯。そして夢を語ったもの、規約、事業報告、事業方針、小グループの活動です。」 西川さん 「それをいただいた人は自動的に会員ということで、年会費は千円です。」 |
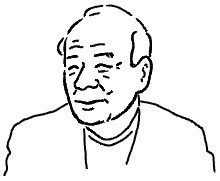 |
||||||||
| 丹波さん 「永源寺の森で『山彦ワークショップ』というのをついこないだやったんです。山の方との意見を交換したり、アイデアを出しあったり、地元の人に山菜ご飯とみそ汁をつくっていただいて。」 |
|||||||||
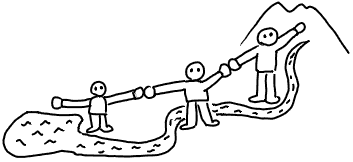 |
|||||||||
| 西川さん 「われわれの活動は西の湖が中心なんだけど、やっぱり上流とも流域としてのつながりも必要で、これは上流の方との第1回の交流になっている。」 |
|||||||||
| 丹波さん 「秋田県立大学の鈴木先生の『森と森の暮らしの再生』というお話があって。この方は近江八幡在住なんです。奥さんは源氏物語の研究で2人とも会員になっていただいているんですが、おもしろい方です。秋田と山形の山を活性化するための『まちおこし』の事例紹介を中心にご説明をいただいたんです。」 「それからミニフォーラムをやったんですが、これがすごいんです。」 |
|||||||||
 |
「80才になる女性がいらっしゃって、昭和50年に、山でご飯が食べられなくなって、主人がサラリーマンになって山を出ていってしまったんだそうです。その間、女性だけで山を守ろうと『あすなろ会』というのをつくられましてね。それで今日までがんばって80になってしまったというんです。」 |
||||||||
| 「だけど去年の台風で、山の木がそれこそつまようじをばらまいたようにみんな倒れてしまって。それ以来、もう山には行っていませんと、山の実情を話してくださった。」 |
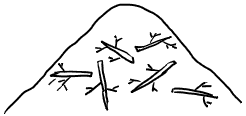 |
||||||||
| 「そうすると、その話を聞いていたまわりの人たちが『みんなでがんばろうよ』と。池田牧場で元気にやっている人の話。安土で建築設計をしていて、永源寺の木を使って家を建てたいとがんばっている人の話。山形から永源寺に来られて、木工の作品をつくっている共同作業所で子どもたちに教えたりもされている。」 「そんな話をしていると、山の方が、『みなさんと話し合って元気が出てきました』『そしてみなさんに、お願いがあります、ちょっとずつ私に寿命をください』とおっしゃったんです。『そして、元気を出して、また山へ入って山を守ろうと思う』と。」 「こういうワークショップを重ねながら、東近江の人たちをまとめて、環境市民会議ができたらいいなと。こういうふうに思っていましてね。」 |
|||||||||
 |
同じようなたくましい“思い”のある人が集まってくれば、何かが必然的にはじまっていくような気がしてきますね。 この写真はアイスクリームをつくっているんですか? |
||||||||
| 丹波さん 「それはアイスクリームじゃないんです。池田牧場の奥さんが、水を入れないで牛乳だけでジェラートをつくっておられるんです。“アイスクリーム”と言うと機嫌が悪いんです。」 |
|||||||||
| 「湖沼会議の関連行事としては、会員がそれぞれ小グループの活動の結果などをパネルで提供してくれたり、環境の狂言では、夏の続編をやったんです。これが好評で世界水フォーラムでも2部を通しでやろうということになったんです。県もお金はないけど、何とかお互いに工面して、通し狂言をやろうよということになったんです。ヨシ舟プロジェクトもどうぞやってくださいとなって。」 |
 |
||||||||
| 「それから、まだこれからの話ですが『西の湖美術館』構想というのがありまして、建物は何も建てないで、西の湖を美術館にしようというんです。」 |
|||||||||
 |
西川さん 「この『西の湖美術館』構想ですが、ある雑誌の巻頭言を頼まれていまして、その雑誌というのが滋賀県の造園技術者協会というところが発行しているんです。で、ぼく、ネタが無いので、これを使わせてもらおうと。雑誌の性格にピッタシかなと思ってるんです。」 |
||||||||
| 丹波さん 「そんなネタが無いなんてことは。でも、ぜひぜひお願いします。」 |
|||||||||
|
(次回につづく) |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 丹波さんが会長を務めている東近江水環境自治協議会の設立趣意書の一部と設立までの経過を紹介します。 東近江水環境自治協議会 設立趣意書(平成12年4月) 私たちは、長命寺湾や、西の湖の周辺や、これらの湾や湖に注ぎ込む川の周辺に住んでいます。そして、いろいろな思いのもとに、そう遠くない昔の長命寺湾や、西の湖を取り戻したいと、これら周辺住民有志により東近江水環境自治協議会(以下水環境自治協議会といいます)を立ち上げることにいたしました。 1.いろいろな思いとは。例えば次の様なことです。 多種多様な魚が戻ってきてほしい。 多種多様な植生を、美しいヨシ原を取り戻したい。 溜まったヘドロを取り除き、美しい水底を取り戻したい。 美味しい飲み水を取り戻したい。 もう一度泳いだり遊べる水辺を取り戻したい。 魚が棲みつき、蛍がまた見られる川にしたい。 梅花藻がまた見たい。 ・ ・ そして、琵琶湖を、多種多様な「いのち」満ちあふれる母なる湖にしたい。 2.では、なぜそのように思ったのでしょうか。 貝が死に、「もろこ」が来なくなっている。ヨシ原は減り、ヒシが消えた。・・・ 水が汚れたらやがて体が汚れ、体がよごれたら「いのち」がいたむことを直感的に感じ、大変なことが起こっているとわかりだしたのです。 今までは、汚い溝には蓋をする。川に流して目に届かぬところに送り込む。後は、行政がそして自然が何とかしてくれる。と思っていました。 しかし、そうではなかったと気が付いたのです。自然が変わってきています。「いのち」の永続と種の多様性を妨げる方向に変わってきています。これらの変化のほとんどは、人間の営みによってもたらされるものです。それが自分達の健康に、いのちの永続に跳ね返ってこようとしています。 今、このような変化に気が付いた人々が声を上げないと、えらいことになると思いだしたのです。 設立までの経過 1 長命寺湾・西の湖環境保全協議会が産みの親 (1) 平成8年の暮れ 八日市市・近江八幡市・安土町の2市1町の行政関係職員有志により環境問題に共同して取り組むニーズや方法についての話し合いが始まる (2) 平成9年に入って3者の事務レベルの会議を重ね一時は「蒲生野の郷(環境保全協議会)」の設立を進めるところまで進んだが 最終的に八日市市が不参を表明 (3) 平成9年12月5日近江八幡市を安土町で長命寺湾・西の湖環境保全協議会発足 (4) この保全協議会は「長命寺湾・西の湖の現状と課題」「長命寺湾・西の湖特定流域総合保全事業計画書」など長命寺湾から西の湖にかけての水域の現状把握と対策を検討する一方で住民対象の「わがまち水辺観察会」を4回に亙って実施 2 9回に及んだ東近江水環境自治協議会の設立準備会 (1) わがまち水辺観察会に参加したメンバーのなかから近江八幡市、安土町各10名の設立準備委員を長命寺湾・西の湖環境保全協議会が人選された そのメンバーにより平成11年11月4日から平成12年7月6日にかけて9回の設立準備会を開催した (2) 設立準備会では 1.準備委員の水環境の改善についての「おもい」を語り合う 2.この「おもい」をもりこんだ設立趣意書を作成する 3.規約案を作成する 4.活動指針案を作成する 5.平成12年度事業計画案を作成する という順序で準備を進める (3) このような経過を経て、平成12年7月8日(土)設立総会を開催し東近江水環境自治協議会が発足した |
|||||||||
|
Copyright (C)2001 Biwako
Shimin Kenkyusho all rights reserved
|
|||