西川嘉右衛門商店会長
| 西川嘉廣さん 西川嘉右衛門商店会長 |
|
|
|
| 第39回 |
お互いにヨシ!の地産地消 |
| 2002年5月9日 菱川貞義 |
| 丹波さん 「『西の湖美術館』構想は、2月11日に発足宣言をして、毎月第2週の土曜日に清掃整備を我々の手でやっていこうと。それから行政を巻き込み、地域を巻き込んで、あまりお金をかけずに周遊の整備をしたい。昔の日本人はみんなやっていたことなんですから。里山をつくったのも昔の日本人。みんなが出てつくってきたわけです。」 |
|||||||||||
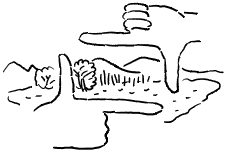 |
自然をそのまま楽しむという西の湖美術館は、とてもおもしろい構想ですね。 西川さん 「そして、いろんな方との連携が生まれています。」 |
||||||||||
| 丹波さん 「我々の事業目的のひとつに、東近江地域などの他グループとの連携強化があります。また東近江環境保全ネットワークや東近江地域振興局との連携強化。まず山彦ワークショップをやって、次に川彦ワークショップをやろうと。テーマは“田んぼと田んぼの再生”、水田の再生です。それで不耕起あるいは有機農業のワークショップをやろうと。我々の理事でこれを進めているのが、たねやの額田さん、それから能登川の岡田麻の岡田さん、それから専業農家の仲岸さん。」 「それから、日野川の水質を考えるシンポジウムのグループ、こういった人たちといっしょになって。それと湖彦(うみひこ)ワークショップ。それはここの大中で、重野さん、竹田さんたちがおられて、有機とかヨシとか水草がある。生ゴミ、し尿、造園業者さんの木の選定くず、それで有機肥料をこさえて、有機の野菜をつくろうと。」 |
|||||||||||
| 「ほかにもこだわって一生懸命つくっている、牛乳、アイスクリーム、肉づくり。それと鶏も。そして“つくる”と同時に地産地消ですね。東近江の地でつくったものをまず東近江の地で消費する。そういうふうに生産者と消費者の間が目に見えるような、そしていつでもオープンにしておいて、“どうやってつくられているのか”というのが見える関係を再構築しようじゃないか。」 |
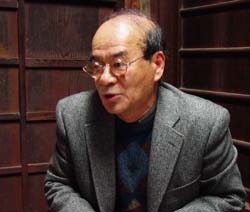 |
||||||||||
| 「第一次産業の方を中心にして。山の再生、森の再生、田んぼの再生、ヨシ原の再生、漁業の再生をめざして、いろんな人たちをゆるくつないで、勉強会をしていく。大風呂敷なんですけど。」 「それがひとつと、もうひとつあるアイデアが、永源寺の木で家をつくる。そして里山の竹、ヨシをもとに土壁を、そして屋根に八幡瓦をのせる。」 |
|||||||||||
 |
ヨシ葺きじゃないんですね。 「建築基準法上ダメなんですよ。でもそれも働きかけて。英国なんかだーっと残ってるんですから、復活させたい。家も、山の木を材木にする人、それで建築する人、それを消費する人、廃棄物を処理する人、そういうふうなサイクルをつくりあげたい。」 |
||||||||||
| 西川さん 「目に見える循環型の社会。」 丹波さん 「これは木を大事に使う家なんです。木材を中心としたサイクルを考える。いまは家が傷んだらつぶしてゴミにしてしまうが、木の住居はつぎ足しができる。そうやって100年もつ家にすれば、100年で木を育ててまわっていけるはずです。」 |
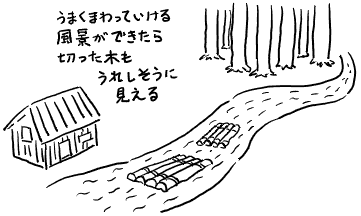 |
||||||||||
|
(次回につづく) |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| 2002年4月21日(日)に恒例のヨシ文化懇話会が西川邸で催されました。テーマは「ヨシと料理」です。 ヨシと料理について・ヨシ文化懇話会 |
|||||||||||
 |
参加者は、川村さんと辻村さんが用意されたヨシの葉100%のお茶とヨシの新芽をゆでたものをおいしくいただいたようです。うらやましい。行きたかった! |
||||||||||
 |
お茶も新芽もその採取時期や調理方法を少しずつ変えて試し、記録も詳細にとられていて、わかりやすくまとめられていたそうです。 |
||||||||||
| 「ほかにも葉の幅広い利用を考えてみてはどうだろうか?」という意見も多く、入浴剤やビール(糖分が多い為)といったアイデアが飛びだしました。また「ヨシに含まれているビタミンCやルチン(毛細血管を強化)を利用したい」という意見も。 「ヨシは食べられる」というぐらいしか、ほとんど文献が残っておらず、またヨシを守り育てながら実際に「食べられるヨシ」を日常に活用できるようになるまでには、たいへんな研究が待ち受けていることだと思います。しかし、とても楽しそうで、有意義なこの研究に、あなたも参加してみませんか?あなたが参加することで、また1歩、「ヨシとなかヨシ」のくらしが近づいていくのです。 くわしい調理方法やヨシの研究については、ヨシ商品開発プロジェクトなどで次々と紹介されると思いますので楽しみにしてください。 |
|||||||||||
 |
|||||||||||
 |
|||||||||||
|
Copyright (C)2001 Biwako
Shimin Kenkyusho all rights reserved
|
|||