西川嘉右衛門商店会長
| 西川嘉廣さん 西川嘉右衛門商店会長 |
|
|
|
| 第43回 |
なぜ、ヨシ!と言ってくれないのですか? |
| 2002年6月6日 菱川貞義 |
| 丹波さん、こんなに一生懸命になっておられるのはどうしてなんですか? |
| 丹波さん 「これまで50年かけて『こういうくらしをしたい』と思って一生懸命やってきました。けど、こんな年寄りになって、振り返ってみたらこれは何だったか。『昔のほうがよかった』じゃないかと思って。」 「それでいま、昔のくらしを取り戻すために『みんなでちょっともがいてみようよ』と集まっているんです。この地域が仲良くなると、住宅、食のサイクルができるんです。それを町の垣根を取っ払ってやらないと。」 |
 |
| 「東近江には日野町、八日市、五箇所、能登川、近江八幡、それぞれ近江商人の拠点がある。それぞれをもとに近江商人の文化が残っているはずだからすごい地域なんです。」 |
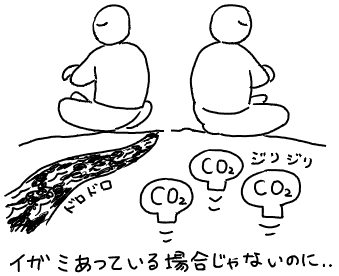 |
「近江商人の伝統は何かというと、これからの時代に必要なものばかり。ひとつは“好奇心”でしょ。2つめは“進取の気性”、3つめに“創造性”、4つめは“自立心”、5つめは“三方よし”、倫理観。そういったいいものをルネッサンスとして残そうと。なのに、あの組長とこの組長は仲が悪いからいっしょになれないとか、虫が好かんとか、そんなしょうもないことで進まんのですよ。そんなのは両方とも悪いんです。」 |
| ぼくもそこのところがひじょうに歯がゆいんです。地球のための、みんなのための環境とくらしに“待った”をかけている連中は見事にスクラムを組んでいるのに、“みんなの環境”を考えているはずのグループがバラバラなんです。びわこ市民研究所は、みなさんのように何かについて具体的に取り組んだりしていませんが、みなさんの貴重な活動をまわりに、そして未来につないでいきたいと思っているんです。 西川さん 「いろいろあるけど、少なくとも安土と近江八幡がいっしょになって欲しい気がします。もともと安土の町が近江八幡に移ったんですから、親戚なんです。」 丹波さん 「安土と近江八幡は同じ地名が多いんです。」 それは気づきませんでした。 西川さん 「歴史背景からいっても、いまのおどろおどろしい関係は末梢的なことだと思う。」 丹波さん 「西の湖をひとつの交通手段として、昔は行き来がすごくあったんです。舟で円山から安土へ嫁が来たり、お米を運んだり…。」 西川さん 「いまは道ができて、かえって交流が無くなった。」 なんとも悲しい話です。 |
| (次回につづく) |
|
|
| 2002年5月26日(日)安土町公民館で東近江水環境自治協議会の主催により 「琵琶の湖(うみ)その後」 が上演されました。 |
|
 |
人間の勝手で、西の湖に連れてこられただけのブラックバスとブルーギルが琵琶湖を追われ、同じようにアメリカを追われたヒゴイとの出会いを通して、根本的な環境問題への気づきや学びをぼくらにもたらしてくれました。 |
 |
大蔵流狂言師の木村正雄さんが、「狂言は、冗談といいながらお上に対してでも真実をつきつけられる」とおっしゃっていましたが、ぼくも狂言のようなコミュニケーション手段の必要性を強く感じました。びわこ市民研究所も、「名もない市民がやっていることだから」といいながら真実を語れる場でありたいと思います。 |
|
Copyright (C)2001 Biwako
Shimin Kenkyusho all rights reserved
|
|||