岡田麻株式会社・代表取締役
| 岡田守弘さん 岡田麻株式会社・代表取締役 |
|
|
| 第4回 |
日本では難しい麻の栽培 |
|
2002年5月30日 坂本 隆司
|
| 利用価値が高く、日本の文化にも深い関係がある麻ですが、現在日本国内での栽培は、一部の神事や研究・種子保存の目的でごく小規模に栽培されているだけです。もちろんこれは大麻取締法により、厳しく規制されているためです。 1948年に第二次世界大戦後のアメリカ占領下のGHQのもとで大麻取締法が制定されました。その結果、大麻を栽培するために毎年、都道府県知事の交付する免許が必要となりました。免許制度と同時に、戦後の石油由来の生活用品の普及によって、植物由来の大麻製品は、次々と姿を消していきました。そして、大麻を栽培する農家が徐々に減少しました。まさに大麻は、50年間で絶滅の危機にある栽培種となっています。 |
| 岡田さん― 大麻の栽培は、使用目的と栽培場所とをはっきりさせて都道府県知事に申請して免許を受ける必要があります。昔から栽培していらしゃって、種の保存のために大麻を栽培している、そんな畑を見学したことがありますが、やはりとても管理が厳しいんですね。葉っぱ一枚外に出てはいけませんから、刈りとる時も役所の人が立ち会いに来ると言ってました。そのように厳しいですから産業用として栽培しようと試みる人はいないですね。コストもかかりますし、普通の農業としては、現状ではとても無理でしょう。ですから、日本での大麻の栽培は法律がある限り難しいですね。 |
|
| でも、これだけ役に立つものですから、さまざまな形で働きかけていくということは必要だと思うんです。地域で作ったものを地域で使っていくというネットワークづくりは何かにつけて必要だと思うんです。大麻はいろいろと難しい問題がありますから、私は規制が掛からない苧麻(ちょま)でいいと思うんです。 |
| 苧麻(ちょま)も大麻と同じ様に繊維のほかにもいろいろと利用価値のある植物ですね。前々回、岡田さんに教えてもらいました。でも一般には麻といえば大麻を連想して、ちょまや亜麻(あま)についてはそれほど知られていないですね。 岡田さん― そうですね。もっと麻について知ってもらうことが大切だと感じています。家業を継いだ頃は、大量流通の時代で我々も量販店に商品を出していましたが、だんだんと繊維業そのものがやや下火なってきて、競争時代に入りました。そこで差別化商品、いわゆる麻というのなんなんだということをもう一度商品の中に謳っていこうとしました。我々もいろんなテストをして、麻の特性とか、麻のメリットとかこんなことに使われてますよ、とか説明を商品に付けて売っていこうとしました。これまでと同じように売ってたら、お客さんも「ああ、麻か」というだけで理解もしないまま買わはると思うんです。麻の良さとは何か、麻てどんな性質があるか、ということ商品に付けて販売していったんです。今でもそうしてます。 繊維や食料としての麻の有効性と共に、これからの時代、環境面でも麻が果たしていける役割は大きいですね。 |
| 岡田さん― ええ、まだ環境としての麻の側面は注目されていない頃なんですけれども。ある講演会を聞きにいって、ヨーロッパの方で麻が環境素材として使われていると聞いたんです。あとで講演者の方に直接お話を聞きに行って、ヨーロッパなどでは環境面からの取り組みが実際に始まっていると知ったんです。それからですね、環境素材として麻をもう一度見直そうと考えたのは。確かにそうですね。麻のロープが今はナイロンになって、ホースとかにもマニラ麻が使われていたのが今はナイロンとかポリエステルとか。それだけ見ても、昔は麻縄かワラの縄しかなかったものが今は全部ビニールのものになってますね、これが全部麻にかわっていけば環境とか自然にいいじゃないかと。 |
|
| それじゃあ一度、麻の研究をやろうということで、麻の研究会を立ち上げました。会合には30人ぐらいが集まりまして、東京・広島・徳島から、わざわざ車で徹夜で走ってこられた人もいて充実したものになりました。そういう研究の一方で、昔の人は産業として連綿とやってきたわけで、環境と産業をひとつにして広がっていくような活動、これがポイントだと思います。これからものを作るにしてももう一度原点に帰った暮らしを考えながら新製品を開発していくと何かうまれるんじゃないかとそういうふうに思っています。昔の人たちの知恵には、いろんな知恵があります。これを生かしながら、今のテクノロジーを加えてより発展的なものに変えていくか。それが産業を活性化するための条件だと思うんです。 なるほど、産業として市場で競争力が無いことには広く受け入れてもらうこともできず、結局一部のものに止まってしまう恐れがありますからね。いろいろ教えてもらいました。麻の話は知らないことも多く、おもしろいですね。 |
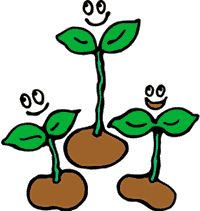 |
麻の有用な点は数多くありますが、ポイントをまとめると次の3つになると思います。 (1)利用価値が高い 衣類、食品、燃料、建材、紙、工作材料などに利用でき、新しい製品・利用法も開発され、広がりつつある。 (2)日本の文化・風土に関係深い 神社、伝統儀式、相撲で古くから使われており、伝統を持つ。 (3)環境に優しく栽培が簡単 埋めれば土に帰り、燃やした時に出るCO2の量も成長の過程で取り込む量とほぼ等しい。綿花のように農薬の使用量も綿花に比べて遥かに少なくてすむ。 |
| 麻と言うと一般的にはどうしてもドラッグとしての大麻を連想しがちですが、麻の主要な品種である苧麻(ちょま)や亜麻(あま)は向精神性効果を持ちませんし、大麻でもそのような成分を含まない産業用大麻が開発されており、ヨーロッパやオーストラリアでは麻を有効に活用した産業化が盛んだと聞きます。これだけ有効な植物が日本では少量しか栽培されていないのは残念なことです。麻のことをもっと知ることが大切だと感じました。 |
|
(つづく)
|
| 『麻』ひとくちメモ 麻の用途のひとつに、紙の原料があります。中国前漢の時代(BC2世紀頃)には、黄河の流域で麻から紙が作られていたとされ、漉く(すく)という紙の製法は、この頃に始まったと言われています。この当時の紙は、銅鏡等を包むためのもので、その後品質が改良され、字が書ける素材としての紙が誕生し、世界へ伝わったようです。日本にも伝わり、伝統的な和紙は大麻と桑の繊維から作られました。現在、木材パルプの供給源として、熱帯雨林の破壊が問題になっていますが、1ヘクタールの麻は4ヘクタールの森林と同じくらい多くの紙を製作することができるといいます。再生が容易な麻はその面でも環境保全に貢献できるものと期待されています。 |
|
|
|||