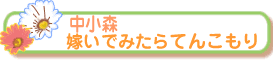
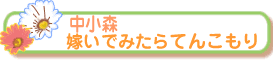 |
第2回 |
| 2002年5月2日 東恵子 |
「もののけ」の竹やぶを越えて 近江八幡市中小森町は、近江八幡駅から西へ徒歩30分の田園地帯。大阪市内まで通勤していた4カ月間は、帰りが午後8時くらいだったので自転車で帰るのが恐い恐い。 自宅の手前にはいかにも「もののけ」が棲んでいそうなうっそうとした竹やぶがあります。おまけに街灯がほとんどないので暗く、遮る建物がないので吹き付ける風の強いことこの上ありません。 |
|
|
| 歴史をちょっとかじると |
| ここで中小森町の歴史を少し紹介します。江戸時代〜明治22年頃までは、「蒲生郡中小森村」と言いました。明治22年には蒲生郡桐原村中小森という大字になり、昭和29年まで、桐原村の大字名になっていたそうです。そしてその後、めでたく(?)近江八幡市中小森町になりました。 「桐原」という地名は今も「桐原学区」と言う学区名に残されていて、桐原学区は、中小森・赤尾・日吉野・大森・森尻・若宮・竹・東村・池田本町・住吉・上野・益田・八木・古川・安養寺・堀上の16の地域に分かれています(新興住宅を除く)。 中小森もまた私の住んでいる北出・新出・東小森・向在家・西出の5つの小路に分かれているんですよ。とにかく、どこがどう分かれているのか、まだまだ覚えられません。 |
|
|
熊沢蕃山さんてどんな人? 中小森町の人が誇りとしている事の一つに「熊沢蕃山さんが住んでいた」ということがあります。私は不勉強なため、「誰、それ?」って感じで驚くこともなく、すごい! なんて思うこともなかったのでした。それに、蕃山さんが「儒学者」と聞いても「儒学って学生時代に習った気がするけど、どんな学問だったっけ?」という程度です。 |
|
中小森町に住んでいたのは、岡山を退いた後の6年間のようですが、くわしいことは、いずれ調べて紹介したいと思っています。 中小森町向在家の森の中にある蕃山さんの住居跡には、昭和の初め頃に石碑が立てられ、約20年前には、地元の老人会の人らによって略歴を記した看板が設置されました。付近もきれいに整備されていて、今も深く尊敬され続けていることがわかります。 |
| 江戸時代、はげ山に植林 |
| 蕃山さんの備前での仕事ぶりを調べていて驚きました。備前では当時、製塩や陶器作り、寺院の建設などのために山林を切り開いていましたが、彼は山林を治水、治山という生活環境の「保険」として必要であると訴えて、藩の費用ではげ山に植林するなどの活動を進めたそうです。 今でこそ「自然は一度手を加えると、もうもとには戻らない。自然環境を守ろう」という考えが増えていますが、江戸時代に実践した人がいたなんて! 終わってしまったテレビ番組「知ってるつもり!?」で取り上げてほしかったなあ。 |
|
|
「信じることを実行しなさい」 「我は我、人は人にてよく候」 |