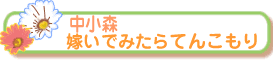
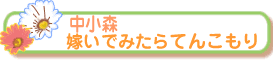 |
第3回 |
| 2002年6月6日 東恵子 |
滋賀県の「祭」文化 滋賀県は周囲に山地をめぐらした盆地で、中央には淡路島よりもはるかに広い面積の「琵琶湖」がどっしりかまえています。地形的にも、近畿と東日本を結ぶ役割を果たしていて、人と物の移動の通過地点でした。そんなわけで近江(滋賀県の昔の呼び名)は、様々な文化交流の舞台となってきました。祭も、そんな交流の中で育まれた文化の一つです。私の住む近江八幡市にも、1年を通してたくさんの祭が行われることを嫁いで初めて知りました。代表的な祭である「左義長祭(さぎちょうまつり)」を2回に分けて紹介します。 |
| 盛大な「左義長祭」 |
| 近江八幡市では、その年の豊穣と幸福を祈願し、災厄防除を求めて町や村のあちこちでお祭りが繰り広げられます。春を告げる天下の奇祭として、全国的にも有名なのが「左義長祭」です。ちょっとその歴史を振り返ってみますと……。 織田信長(1534〜82年)が今の滋賀県安土町に安土城を築いたことは知られていますよね。毎年正月、信長は安土城下で盛大に「左義長祭」を行い、自身も化粧をし派手な衣装で踊り出たそうです。 信長が亡くなった後、豊臣秀吉の甥・豊臣秀次(1568〜95年)が「八幡山城」を築きました。近江八幡は、それにつられて安土から移住して来た人たちを中心に開かれた町で、日牟礼八幡宮(ひむれはちまんぐう)の左義長祭も彼らによって伝わったのです。 |
|
|
余談ですが、秀次は、城下に堀を築き、町を碁盤の目のように整理するなど町の発展に貢献しました。しかし、秀吉に実子・秀頼が生まれたことで甥の秀次は疎ましがられ、ついには「謀反を企てた」という理由で一族すべてが処刑されてしまいました。 秀次の母(秀吉の姉)・瑞龍院日秀尼公は、秀次の鎮魂のため、京都・村雲に「瑞龍寺(ずいりゅうじ)」を創建しました。このため瑞龍寺は俗に「村雲御所(むらくもごしょ)」と呼ばれています。 |
| 1962年、八幡山城が築かれていた八幡山頂に移されました。京都から移された庭園は名庭と言われています。山頂からは、近江富士とも呼ばれる「三上山(みかみやま/432メートル)」や鈴鹿連山、琵琶湖が一望でき、市内随一の眺めと言われています。 |
|
|
|
語源は「悪魔退散」? |
| さて、「左義長」は、もとは小正月(1月14,15日)の行事で、門松やしめ飾りなどを焼く「どんど焼き」のような祭として全国各地で行われるようです。仏教と共に中国から伝わり、宮中の儀式として各地で流行したといいます。 語源について調べてみました。 「三本の木を組んで、その脚を三方に張ったため、三木帳と称した。後世、文字も変化し形も変わったのでは」という説がありました。 |
|
| また、ちょっと難しい説があったので紹介します。中国最初の寺「白馬寺」で、道教の教義を右に、仏教の教義を左に置いて祈願し火をつけたところ、右は焼け、左は全く焼けなかったところから「左に置いた教義が長じていた」という所から「左義長」と言われるようになったというのです。 悪魔退散のための「散鬼杖」からきている、という説も。左義長に使われる青竹が火にあぶられて爆竹音がするところから、悪魔を退散させるというふうに考えられたのでは、とのことです。 左義長を燃やす「奉火」は本宮(2日目)の夜です(今年は3月17日でした)。残念ながら今年は行くことができず、音を聞くことができませんでした。来年はぜひ、間近で見て「悪魔が退散する音」を聞きたいものです。 |
|