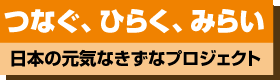
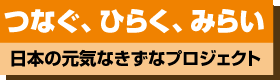 |
|
| 第7回 山と人とのつながりを、次の世代に引き継ぎたい |
| 2013年11月10日 菱川貞義 |
山門水源の森を次の世代に引き継ぐ会 |
長浜市西浅井町山門に山門水源の森があります。日本海と太平洋の両方からの風を受け、生物多様性に富む、山門水原の森。氷河期の生き残りも見られる貴重な湿原。これらを次の世代に引き継ぐために活動しているのが、「山門水源の森を次の世代に引き継ぐ会」です。1987年に山門湿原研究グループが地質・植生・昆虫等について調査をしたことが契機となり、今日まで地道な活動が展開されてきました。 森は、ブナ林・ミズナラ林・アカガシ林・コナラ林・アカマツ林・スギ・ヒノキ林の多様な林で構成されており、暖帯のアカガシ林と温帯のブナ林が隣接している大変珍しい森です。森の中心には、近畿でも珍しい高層湿原である、山門湿原があり、貴重な植物が残っています。
|
竹端康二さん(会長) わたしは、ずっとここに住んでいて、山ともかかわってきましたので、役目として、昔と今のちがうところを伝えています。
橋本勘さん(理事) ここでの活動は五年目ですが、会のなかでは、わたしは若いほう、というか、いちばん下っ端です。山の活動をもっと続けよう、とか、いつになったらやめよう、とか、そういうのはなくて、もう生活の一部になっています。山では作業もしますけど、ぼくにとっては、大切な観察する場所になっています。何もないようで、見る人が見るとすばらしく変化しているのがわかるんです。
藤本秀弘さん(事務局長) ここは、ちょうど日本の南と北の中間点なんです。絶滅危惧種とか、貴重な生物群あり、生物多様性のある貴重な資源だと認識されてきました。
|
|
活動紹介毎月第3土曜日は保全活動の日です。9月は会員10人と地元中学生12人。さらに、淡海森林クラブからの5人も駆けつけてくれました。台風18号は、北部湿原へ大量の土砂流入をもたらしました。その土砂の撤去や森の林床整理がメインの作業です。 この湿原は、ブナ、アカガシ、コナラなどが生える森林に囲まれています。1960年代後半まで、長い間薪炭林として利用されていた里山です。その後、人びとは炭焼きをやめ、湿原で芝生を生産しようと、土砂を入れたり水の流れも変えたりしました。幸いにしてその事業は中止されましたが、湿原は水が少なくなり、林になりつつありました。 |
|
ところで、保全作業は力仕事ばかりではありません。ミツガシワやササユリなどの植物を、シカ、イノシシ、ノウサギなどの食害から守るための網掛け、トタン張り、種まき、育種というのもあります。動物たちの食害から植物を守る、というのはなかなかむずかしいもので、次々と新しい工夫をしなければなりません。
|
|
地域のみなさんやいろいろな団体の協力もありますが、わたしたちは、まだまだ、微力です。今後とも多くの方のご理解、ご協力をお願いいたします。
|
|
|
|
| つづく |